トピックス
ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、
最新情報をお知らせしています。
2025年10月5日
喪中はがき、これで完璧!時期、文例、切手の選び方|喪中マナーの基本
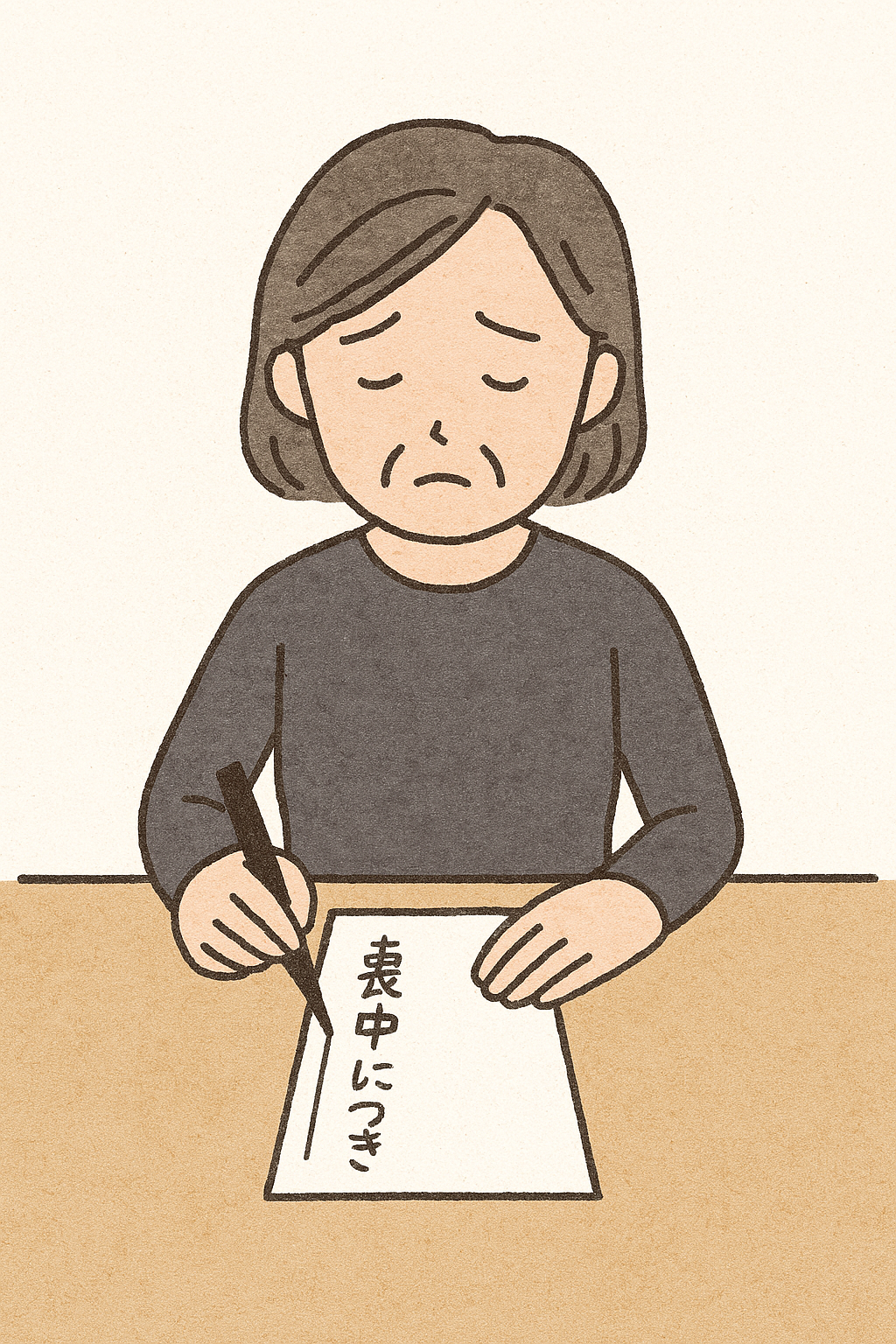
大切な方を亡くされた喪中の方へ。年末年始の挨拶を控え、喪中はがきを出すにあたり、「何を書けばいいの?」「どんな切手を使えばいいの?」と悩んでいませんか? 本記事では、喪中はがきの基本的なマナーから、失礼のない書き方、切手の選び方まで、喪中はがきに関するすべてを分かりやすく解説します。喪中の方も、喪中はがきを受け取った方も、この記事を読めば、年末年始の挨拶を安心して迎えることができます。
喪中はがきとは?基本的な意味と役割
身近な方が亡くなられた際、遺族は一定期間、故人を偲び、静かに過ごす「喪中」に入ります。この期間は、一般的に四十九日法要などを終えるまでとされますが、忌明け後も、正月三が日(1月1日~3日)の間は、お祝い事を控えるのがならわしです。
「喪中はがき」とは、このような喪中の期間にあたるため、年末年始の挨拶(年賀状の交換)を辞退する旨を、お世話になった方々や親しい友人・知人に伝えるための挨拶状です。本来、年賀状は新年の慶びを祝い、互いの健康や幸福を祈るためのものですが、喪中の期間にこれを行うことは、故人への配慮に欠けると考えられています。そのため、喪中はがきを事前に送ることで、相手に年賀状を差し控えていただくよう、丁寧にお願いするのです。
このはがきは、単に年賀状を辞退する意思表示にとどまりません。亡くなった方への追悼の気持ちを表し、遺族が喪に服していること、そしてその期間においては礼儀としてお祝いの言葉を控えるべきであることを、周囲に伝えるための重要な役割も担っています。故人を偲び、静かに弔いの期間を過ごしたいという遺族の心情を理解していただき、温かく見守ってほしいという願いが込められています。
初めて喪中を経験される方や、喪中はがきのマナーについて不安を感じている方にとって、その意義を理解することは、故人への敬意を払い、周囲との円滑な関係を保つ上で非常に大切です。喪中はがきは、日本の伝統的な弔いの文化と、人間関係における配慮を示す、心遣いの表れと言えるでしょう。
喪中はがきを出す時期と範囲
喪中はがきは、近親者が亡くなった際に、新年の挨拶を控える旨を伝えるための大切な通知です。このはがきを適切な時期に、適切な範囲の方へ送ることは、故人への追悼の意を示すとともに、送られた方々への配慮を示す重要なマナーとなります。ここでは、喪中はがきを出すのに最適な時期と、送付すべき範囲について詳しく解説します。
喪中はがきを出すのに最適な時期
一般的に、喪中はがきは立冬(りっとう)から12月15日頃までに届くように送るのが良いとされています。立冬は二十四節気の一つで、例年11月7日か8日頃にあたり、冬の始まりを告げる日です。この時期に送ることで、受け取った方が年末年始の挨拶を控えるための十分な時間を確保できます。
喪中期間は、一般的に故人が亡くなった日から1年間とされています。そのため、例えば1月1日に亡くなった場合、その年の年末年始は喪中とはなりません。しかし、1月2日以降に亡くなった場合は、その年の年末年始が喪中となります。 もし、喪中期間の開始時期が不明確であったり、亡くなったのが年末に近かったりする場合は、送付時期について迷うこともあるでしょう。しかし、基本的には「年内に喪中であることを伝え、新年の挨拶を辞退する」ことが目的ですので、年内、特に12月15日までに届くように手配するのが最も丁寧な対応と言えます。12月15日を過ぎてしまった場合は、年賀欠礼の挨拶状としてではなく、喪中であることを伝える「弔い明けの挨拶状」として、年が明けてから送るという方法もあります。
喪中はがきを送付すべき範囲
喪中はがきを送る相手は、故人との関係性や、ご自身との関係性によって判断します。明確な決まりはありませんが、一般的には以下のような方々へ送ることが多いです。
- 親族: 故人の三親等以内の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、叔父叔母、甥姪など)が主な対象となります。ただし、関係性の深さによっては、四親等以上でも送る場合があります。
- 友人・知人: 故人と親しかった友人や知人、ご自身が個人的に親しくしている友人や知人。
- 会社関係者: 勤務先の上司、同僚、取引先など、日頃お世話になっている方々。特に、故人が生前お世話になった方や、葬儀・告別式に参列いただいた方には送るのが一般的です。
- その他: 近隣の方や、年賀状のやり取りをしていた方など、日頃お世話になっている方で、喪中であることを伝えておくべきだと考えられる方々。
一方で、以下のような方々へは、必ずしも送る必要はありません。
- すでに訃報を知っている方。
- ご自身が喪中であることを、すでに相手も知っている場合。
- 相手も喪中である場合。(この場合、相手に配慮して喪中はがきを送らないのが一般的です。)
- 関係性が非常に遠い方や、年賀状のやり取りがない方。
送付範囲の判断に迷った際の対応
喪中はがきを送る相手の範囲は、地域や家庭、個人の考え方によっても異なります。迷った場合は、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 関係性の深さ: 故人との直接的な関わり、ご自身との交流の頻度や深さを基準にします。
- 相手への配慮: 相手が年賀状の準備などを始める前に、喪中であることを伝えるのが目的です。相手が年賀状の準備を始めている時期(12月に入ってからなど)に送ると、相手に手間をかける可能性があります。
- 周囲への確認: 判断に迷う場合は、ご家族や親族に相談してみるのが最も確実です。特に、故人の配偶者や子供が喪主を務める場合、その意向を尊重することが大切です。
喪中はがきの送付は、故人を偲び、新たな年を静かに迎えるための大切な儀礼です。ここで述べた時期や範囲、そしてマナーを参考に、心を込めて準備を進めてください。
喪中はがきの書き方:構成と例文
喪中はがきは、年末年始の挨拶を控える旨を伝えるとともに、近親者が亡くなったことを知らせるための大切な挨拶状です。この形式で送ることで、相手への配慮を示し、故人を偲ぶ静かな時間を過ごしていることを伝えます。このセクションでは、喪中はがきの基本的な構成要素から、相手別の具体的な例文までを詳しく解説し、失礼なく、かつ心のこもったメッセージを作成するためのポイントをご紹介します。喪中はがきの「書き方」をマスターし、適切な「構成」で、心のこもった「例文」を参考に、故人を偲び、新たな年を迎える準備をしましょう。
時候の挨拶(年頭の挨拶を控える旨)
喪中はがきを出す時期は、一般的に11月中旬から12月初旬にかけてです。この時期は、新年の挨拶の準備を始める頃ですが、身内を亡くした家庭では年賀状のやり取りは控えるのが慣習です。そのため、喪中はがきでは、まず相手への新年の挨拶を失礼する旨を丁寧に伝えることが重要となります。これは、お祝いの言葉を述べるべき時期に、不幸があったことを知らせることで、相手に不快感を与えないための配慮です。「新年のご挨拶を失礼させていただきます」や「年頭のご挨拶はご遠慮させていただきます」といった表現を用いることで、相手への配慮を示します。新年の挨拶を控える理由を簡潔に添えることで、相手への理解を求め、失礼にあたらないように配慮することが大切です。
故人の情報
喪中はがきには、故人に関する最低限の情報を簡潔に記載します。一般的には、故人の氏名、故人との関係性、そして亡くなった日付(月日)を記載します。例えば、「〇〇(故人の名前)儀、令和〇年〇月〇日、〇〇歳にて永眠いたしました」といった形が標準的です。故人との関係性は、「父」「母」「夫」「妻」「祖父」「祖母」などと明記します。これにより、受け取った相手は、誰が亡くなったのか、そして故人との関係性を把握することができます。あまり詳細に故人の生前の功績などを長文で記す必要はありませんが、故人を偲ぶための最低限の情報として、丁寧な表現を心がけ、故人を敬う気持ちを込めて記載しましょう。
近況報告
喪中はがきでは、自身の近況を簡潔に伝えることも一般的です。ただし、この時期に詳細な近況報告や、自身の悲しみや苦労について長々と書き連ねることは避けるべきです。喪中期間は、遺族が心静かに故人を偲び、悲しみを乗り越えていくための大切な時間です。そのため、近況報告は、あくまでも相手への配慮を忘れず、穏やかな表現で伝えることが大切です。「おかげさまで、家族一同静かに過ごしております」といった、家族の安否や平穏な日々を伝えるような表現が適しています。詳細な報告は避け、相手を気遣う言葉を添えることで、一方的な報告ではなく、相手との繋がりを大切にする姿勢を示すことができます。
今後の付き合いについて
喪中はがきは、故人を偲ぶだけでなく、来年以降も変わらぬお付き合いをお願いする気持ちを伝える場でもあります。そのため、結びの言葉として、相手への気遣いや今後の関係継続を願う言葉を添えるのが一般的です。例えば、「寒さ厳しき折、皆様もどうぞご自愛ください」といった相手の健康を気遣う言葉や、「来年も変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます」といった、今後の関係を願う言葉を加えます。これにより、喪失感を抱えつつも、前向きに社会との繋がりを大切にしていきたいという意思表示となります。これは、悲しみから立ち直り、新たな年を迎えるにあたり、周囲との関係性を再確認し、育んでいくための丁寧な配慮と言えるでしょう。
相手別の喪中はがき例文集
喪中はがきは、送る相手によって適切な表現や内容が若干異なります。送る相手との関係性の深さや、普段のコミュニケーションのスタイルに合わせて、内容を調整することが大切です。ここでは、親族、友人・知人、会社関係者といった、主な送付先別に具体的な例文をご紹介します。それぞれの相手に合わせた丁寧な表現や、含めるべき内容の違いを理解することで、より心のこもったメッセージを作成することができるでしょう。
親族向けの例文
親族へ送る場合は、故人との関係性が近いこともあり、より個人的な繋がりや、故人との思い出に触れることもできますが、基本的には丁寧さを保ちます。
謹啓
寒冷の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、この度 〇〇(故人の名前)儀、〇月〇日、〇〇歳にて永眠いたしました。
生前は格別のご厚情を賜り、心より感謝申し上げます。
皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
つきましては、年末年始のご挨拶を失礼させていただきます。
本来であれば直接ご挨拶に伺うべきところ、略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
寒さ厳しき折、皆様もどうぞご自愛ください。
今後とも変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
謹白
令和〇年〇月
[差出人名]
[住所]
友人・知人向けの例文
友人や知人へ送る場合は、親族ほど改まりすぎる必要はありませんが、亡くなったことへの悲しみや敬意を忘れずに伝えます。普段の親しみを込めた表現と、喪中の礼儀を両立させることがポイントです。
拝啓
師走の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この度、〇〇(故人の名前)が〇月〇日に急逝いたしました。
〇〇とは〇〇(例:学生時代からの友人)として、共に過ごした日々は私にとってかけがえのない宝物です。
生前は温かいお心遣いをいただき、心より感謝申し上げます。
本来であれば直接お伺いし、お伝えすべきところ、略儀ながら書中をもちましてご挨拶とさせていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
寒さ厳しき折、どうぞご自愛ください。
令和〇年〇月
[差出人名]
[住所]
会社関係者向けの例文
会社関係者や上司、取引先などへ送る場合は、より丁寧で改まった表現が求められます。故人が職場に関係する人物であった場合、その功績に触れることもありますが、簡潔さが重要です。
拝啓
師走の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度、弊社〇〇部〇〇(故人の名前)が〇月〇日に逝去いたしました。
在職中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
ここに謹んでご通知申し上げますとともに、ご霊前へのご挨拶も兼ねてご挨拶申し上げます。
なお、年末年始のご挨拶は、誠に勝手ながら失礼させていただきます。
末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
敬具
令和〇年〇月
[差出人名]
[所属部署]
[住所]
これらの例文を参考に、ご自身の状況や送る相手に合わせて、心のこもった喪中はがきを作成してください。喪中はがきは、故人を偲ぶ気持ちと、周囲への配慮を伝えるための大切な手段です。丁寧な言葉遣いと構成で、感謝の気持ちを込めて伝えましょう。
喪中はがきに使う切手の種類
喪中はがきを送る際、どのような切手を選べば良いか迷うことはありませんか。弔事の際にふさわしい切手を選ぶことは、故人への敬意を表す大切なマナーの一つです。ここでは、喪中はがきに使える切手の種類や、郵便料金、そして選び方のポイントについて詳しく解説します。
弔事用切手・年賀状用切手について
日本郵便では、弔事用の郵便物(お悔やみ状や弔事用のはがきなど)に利用できる「弔事用切手」や、お歳暮・お年玉などの慶事用郵便物に使える「年賀状用切手」が発行されています。喪中はがきも弔事用郵便物に含まれるため、これらの切手を利用するのが最も一般的で、失礼がありません。 弔事用切手は、落ち着いた色合いやデザインが特徴で、喪中の時期にふさわしい雰囲気を醸し出しています。これらの切手は、全国の郵便局の窓口や、一部の郵便局のオンラインストアなどで入手できます。ただし、弔事用切手は常に販売されているとは限らず、期間限定で発行される場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
通常の切手は使える?
では、弔事用切手が見つからなかったり、手元にない場合はどうすれば良いのでしょうか。結論から言うと、通常の郵便切手でも喪中はがきを送ることは可能です。 ただし、切手のデザインには配慮が必要です。お祝い事を連想させるような、明るすぎる色合いや華やかな絵柄の切手は避けるのが賢明です。例えば、桜や紅葉、風景画など、落ち着いたデザインの切手であれば、弔事用として問題なく使用できる場合が多いです。 切手の料金も、はがきの料金に合ったものを選ぶ必要があります。現在の郵便料金は、はがき1枚あたり63円(2024年4月時点)です。切手で支払う場合は、この金額をカバーできる切手、または複数の切手を組み合わせて貼付してください。
郵便料金の注意点
喪中はがきは、通常のはがきとして扱われるため、所定の郵便料金が必要です。切手代が不足していると、相手に届かない、あるいは受け取り時に料金を請求されるといった事態になりかねません。 また、日本郵便では「弔事用郵便料金」として、特定の条件を満たす場合に割引が適用される制度もありますが、これは主に企業から大量に送付される場合などに限られることが多く、個人が喪中はがきを少数送る際には、通常の郵便料金で問題ありません。 最新の郵便料金については、日本郵便の公式サイトなどで必ずご確認ください。
喪中はがき用切手の選び方
喪中はがきに使う切手を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 弔事用切手があれば最優先で利用する: 郵便局で入手できる場合は、これが最も丁寧で安心です。
- 通常の切手を使用する場合はデザインに注意: 落ち着いた色合いや、お祝い事に関係ない絵柄のものを選びましょう。
- 郵便料金を正確に: はがき1枚あたりの料金を確認し、不足がないように切手を貼付します。
- 不明な点は郵便局に相談: 迷った場合は、最寄りの郵便局の窓口で相談するのが確実です。
これらの点を踏まえ、故人を偲び、送る相手への配慮を忘れずに、適切な切手を選んでください。
喪中はがきの印刷方法と費用
喪中はがきは、年末年始のご挨拶を控える旨を伝える大切な年中行事です。いざ準備を始めようと思っても、印刷方法やそれに伴う費用について、どのように進めるのが良いか迷う方もいらっしゃるでしょう。ここでは、喪中はがきを準備する際の主な印刷方法として、自宅での印刷と印刷業者への依頼の二つを取り上げ、それぞれのメリット・デメリット、そして費用感について詳しく解説します。さらに、デザインテンプレートの活用法や、より経済的に、あるいはよりこだわって作成するためのヒントもご紹介します。読者の皆様が、ご自身の状況や希望に合った最適な方法で、心のこもった喪中はがきを作成するための一助となれば幸いです。
印刷方法(自宅印刷、業者依頼)
喪中はがきを印刷する方法は、大きく分けて「自宅のプリンターで印刷する」方法と、「印刷業者に依頼する」方法の二つがあります。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットが異なりますので、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
- 自宅印刷
- メリット:
- 手軽に始められる: 自宅にプリンターがあれば、すぐに作業を開始できます。
- 即時性: 思い立った時にすぐに印刷でき、急な手配にも対応しやすいです。
- コスト(印刷代): 初期投資(プリンター、インク)を除けば、1枚あたりの印刷代は比較的安価に抑えられます。
- デザインの自由度: 市販のソフトや無料テンプレートを利用して、細かくデザインを調整できます。
- デメリット:
- 品質: 家庭用プリンターの場合、特に写真印刷などで業者に劣る場合があります。インクジェットは滲みやすいことも。
- 手間: デザインの作成・調整、プリンターの設定、用紙のセット、印刷後の裁断など、手間がかかります。
- 用紙の選択肢: 用紙の種類や厚さに限りがある場合があります。
- 印刷ミス: 予期せぬ印刷トラブル(かすれ、色ムラ、紙詰まりなど)が発生する可能性があります。
- メリット:
- 業者依頼
- メリット:
- 高品質な仕上がり: プロ仕様の印刷機を使用するため、鮮明で美しい仕上がりになります。
- デザインの豊富さ: 多種多様なデザインテンプレートが用意されており、プロが作成したような洗練されたデザインを選べます。
- 手間がかからない: デザインを選んで注文するだけで、印刷から投函まで代行してくれるサービスもあります。
- 用紙の選択肢: 様々な紙質や厚さの用紙を選べます。
- デメリット:
- 納期: 注文から納品までに数日〜1週間程度かかる場合があります。
- 費用: 自宅印刷に比べると、1枚あたりの単価は高くなる傾向があります。
- 最低ロット: 業者によっては、最低注文枚数が設定されている場合があります。
- デザインの制約: テンプレートによっては、細かなデザイン変更ができない場合があります。
- メリット:
どちらの方法を選ぶかは、かけられる時間、予算、求める品質、そしてデザインへのこだわりなどを総合的に考慮して決定するのが良いでしょう。
費用について
喪中はがき印刷にかかる費用は、選択する印刷方法やサービス、デザイン、用紙の種類などによって大きく変動します。ここでは、一般的な費用の内訳と、それぞれの方法でのおおよその費用感について解説します。
喪中はがき印刷にかかる主な費用は、「印刷代」「用紙代」「切手代」「送料」などです。自宅印刷と業者依頼では、これらの費用の内訳や合計金額に違いが出ます。
自宅印刷の場合、プリンター本体やインクカートリッジ、用紙などの初期投資がかかりますが、一度揃えてしまえば1枚あたりの印刷代は比較的安価に済みます。例えば、インクジェットプリンターで光沢紙やマット紙に印刷する場合、インク代と用紙代を合わせても1枚あたり数十円程度に収まることが多いでしょう。ただし、デザインソフトの利用や、こだわりの用紙を別途購入する場合は、その費用も考慮する必要があります。
一方、印刷業者に依頼する場合、サービス内容によって費用は大きく異なります。シンプルなモノクロ印刷で、汎用的なデザインテンプレートを利用すれば、1枚あたり50円〜100円程度から依頼できる業者もあります。写真入りやカラー印刷、特殊な紙質を選択したり、デザインのカスタマイズを依頼したりすると、1枚あたり150円〜300円以上になることも珍しくありません。また、多くの業者では、基本料金や版代、送料などが別途かかる場合や、最低注文枚数が設定されている場合があるので、事前に確認が必要です。年賀状印刷のオフシーズンである秋口などは、早割キャンペーンなどを利用してお得に依頼できることもあります。
切手代は、官製はがき(郵便局で販売されている喪中用はがき)を利用する場合は、はがき代と切手代が一体となっているため、別途切手代はかかりません。私製はがき(自分で用意した用紙)に印刷する場合は、所定の郵便料金(通常63円)の切手を貼る必要があります。また、投函代行サービスを利用する場合は、その手数料も加算されます。
ご自身の予算に合わせて、印刷方法、デザイン、用紙などを検討し、最も費用対効果の高い方法を選択することが大切です。例えば、枚数が多い場合は業者依頼の方が割安になることもありますし、枚数が少ない場合は自宅印刷の方が手軽で安く済む場合もあります。費用の内訳をしっかり把握し、賢く喪中はがきを作成しましょう。
喪中はがきを受け取った場合の対応
喪中はがきは、近親者に不幸があり、服喪(ふくも)期間中であるため、新年の挨拶を辞退する旨を伝えるためのものです。このはがきを受け取った際は、相手への配慮を示す適切な対応を心がけることが大切です。ここでは、喪中はがきを受け取った際の、返信の要否や方法、お悔やみの言葉の伝え方、そして相手が喪中であることを理解し、年末年始の挨拶を控えることの重要性について解説します。相手との良好な関係を維持するための、丁寧な対応方法を具体的に示します。
返信について
喪中はがきを受け取った場合、必ずしも返信が必要というわけではありません。しかし、故人との関係が深かった場合や、相手に失礼がないか心配な場合は、返信を検討すると良いでしょう。返信する際には、「お悔やみ」の気持ちを伝えることが重要です。返信は、はがきを受け取ってから1週間から10日以内、遅くとも年内(12月中)に行うのが一般的です。返信の方法としては、喪中見舞いのはがきを送る、またはお悔やみの手紙を添えて弔電を送る、お供え物を送るなどが考えられます。返信はがきには、相手への気遣いやお悔やみの言葉を簡潔に記載し、丁寧な「マナー」を守りましょう。
年始の挨拶を控える
喪中はがきを受け取った相手に対しては、年末年始の「年始の挨拶」、特に年賀状や年賀の挨拶は「控える」べきです。これは、相手が服喪期間中であり、お祝い事を受け取る心境にないことへの「配慮」からです。年賀状を送る代わりに、寒中見舞い(松の内が明けた1月8日から立春の前日(2月3日頃)までに送る)やお見舞いの手紙を送ることで、相手を気遣う気持ちを伝えることができます。相手の状況を理解し、静かに寄り添う姿勢を示すことが、良好な関係を築く上で重要となります。
喪中期間中の過ごし方
喪中期間とは、近親者を亡くした遺族が故人を偲び、心静かに過ごす期間のことです。一般的には四十九日法要(満中陰)までを指すことが多いですが、地域や家庭によっては一年間を喪中とする場合もあります。この期間、特に年末年始を迎えるにあたり、どのような心構えで過ごせば良いのか、多くの方が悩むことでしょう。本セクションでは、喪中期間における年末年始の過ごし方、お正月の過ごし方、そして年始の挨拶に関する考え方などを解説します。故人への追悼の意を深め、静かで穏やかな気持ちで新しい年を迎えるための一助となれば幸いです。
お正月の過ごし方
喪中期間中のお正月は、例年とは異なる過ごし方が求められます。一般的に、お正月を祝うための華やかな行事や飾り付けは控えるのが通例です。具体的には、門松や鏡餅の飾り付け、おせち料理の準備・飲食、お雑煮の準備・飲食、年明けの挨拶回りは控えるのが一般的とされています。また、初詣も避けるべきとされることが多いです。これらの習慣は、お祝い事や慶事を意味するため、遺族が悲しみに服している喪中期間にはふさわしくないとされるからです。ただし、地域や家庭によっては、これらの習慣に対する考え方や許容範囲が異なる場合もあります。例えば、家族だけで静かに過ごす、故人を偲びながら普段通りの食事をする、といった形をとるご家庭もあります。大切なのは、故人を偲ぶ気持ちを最優先にし、ご遺族が心穏やかに過ごせるように配慮することです。もし、お正月の過ごし方について迷う場合は、菩提寺の住職や親族に相談してみるのも良いでしょう。
年始の挨拶について
喪中であるため、本来であれば新年の挨拶を交わす時期であっても、年賀状の送付や年始の挨拶は欠礼するのが一般的です。これは、喪中の家庭に対して、お祝いの言葉を述べることを避けるという配慮に基づいています。年賀状の代わりに、喪中であることを伝え、新年の挨拶を失礼させていただく旨を記した「喪中欠礼状」や「年賀欠礼状」を、年末までに送るのがマナーです。これにより、相手に喪中である旨を伝え、年始の挨拶をしないことへの理解を求めることができます。また、年始に親戚や知人宅を訪問する際にも、喪中であることを伝え、お祝いの言葉は控えるようにしましょう。相手に失礼なく、かつ故人への敬意を保つための大切な配慮となります。相手が喪中であることを知らずに連絡をくれた場合には、丁寧にお礼を伝えつつ、喪中であることを伝えることも大切です。このような状況での年始の挨拶は、形式よりも、相手への思いやりや故人への敬意が最も重要となります。
まとめ:喪中はがきのマナーを守り、心を込めて挨拶を
この記事で解説した喪中はがきに関するマナー、時期、書き方、切手、印刷方法、対応などを総括します。喪中はがきは故人を偲び、大切な人たちとの関係を大切にするためのコミュニケーション手段であることを再確認し、読者が喪中はがきに関する不安を解消し、失礼なく、かつ温かい気持ちで年末年始の挨拶を済ませられるようになることを目指します。
喪中はがき印刷 2025年(令和7年) – 郵便局のプリントサービス
https://print.shop.post.japanpost.jp/mochu


 無料資料請求
無料資料請求











