トピックス
お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして終活など、
知っておくべき情報をお届けします。ぜひ活用ください。
2025年10月29日
会葬御礼のすべて:返礼品、礼状、香典返しのマナーを分かりやすく解説
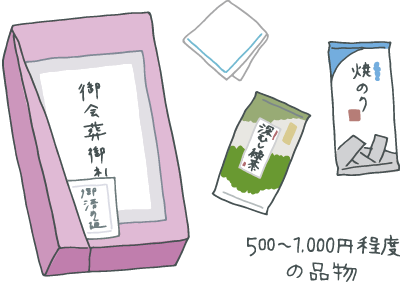
大切な方を亡くされたご家族にとって、葬儀後の対応は心身ともに負担が大きいものです。その中でも、会葬御礼品や香典返しは、マナーや品物選びに悩む方も少なくありません。本記事では、会葬返礼品の基礎知識から、近年の傾向、礼状の書き方、香典返しのマナーまで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、故人を偲ぶ大切な時間を守りながら、故人の関係者へ感謝の気持ちを伝えることができるでしょう。
会葬返礼品とは?その意味と目的
葬儀にご会葬いただいた皆様へ、心ばかりの品をお渡しするのが会葬返礼品です。これは、ご多忙の中、ご足労いただき、お別れの場に参列してくださったことへの感謝の気持ちを表すためのものです。また、お香典を辞退された場合でも、弔問いただいたことへの感謝としてお渡しすることもあります。
会葬返礼品は、参列してくださった方々への直接的な感謝の意を示すとともに、葬儀の準備や当日の対応でご遺族の負担が大きくなる中で、参列者の方々にご負担をおかけしないように、という配慮も含まれています。
会葬返礼品をお渡しする「なぜ」という目的は、主に参列者への感謝の表明です。遠方からお越しいただいた方、お仕事の都合をつけてくださった方など、様々な状況で参列してくださった方々へ、そのお気持ちに対する謝意を形にしてお伝えします。
「何を」お渡しするかについては、近年、実用的な品物や、地域性、故人の趣味などを考慮したものが選ばれる傾向にあります。以前はタオルや海苔、お菓子などが一般的でしたが、最近ではカタログギフトや、食品、日用品など、多様化しています。大切なのは、参列してくださった皆様に喜んでいただける品物を選ぶことです。
「誰に」お渡しするかですが、基本的には葬儀に参列してくださった方、全員にお渡しするのが一般的です。ただし、地域やご家庭によっては、お香典をくださった方には別途香典返しを、お香典を辞退された方や、お香典なしでご会葬いただいた方には会葬返礼品、というように区別する場合もあります。
会葬返礼品の始まりと歴史
会葬返礼品は、葬儀に参列してくださった方々へ感謝の気持ちを伝えるための品物です。その起源や歴史的背景について、関心をお持ちの方もいらっしゃるかと存じます。会葬返礼品がいつ頃から始まり、どのような経緯を経て現在のような形になったのかを解説いたします。
古くから、葬儀に参列いただいた方々へ感謝の印として品物を贈る習慣は存在しました。例えば、江戸時代には、参列者へのお礼としてお茶やお菓子などの「引出物」を渡す風習が見られました。これが、現代の会葬返礼品の原型とも言えるでしょう。
しかし、現代に広く普及しているような、弔問へのお礼としての「会葬返礼品」という形が定着したのは、比較的最近のことです。明治時代以降、社会の変化とともに葬儀の形式も多様化し、地域や家庭によってさまざまな慣習が見られるようになりました。そして、第二次世界大戦後、経済の発展とともに人々の生活水準が向上するにつれて、葬儀の簡略化や効率化が進み、参列者への感謝の気持ちを具体的に表す手段として、会葬返礼品を贈ることが一般的になっていきました。現在では、参列者への感謝を伝えるとともに、葬儀という場を和やかに終えるための一助としても、その役割を果たしています。
近年の会葬返礼品の傾向
近年、葬儀の形式が多様化するにつれて、会葬返礼品についても変化が見られます。故人を偲び、ご参列いただいた方々へ感謝の気持ちを伝えるための返礼品選びは、現代のニーズに合わせて進化しています。ここでは、近年の会葬返礼品選びにおける最新の傾向について、品物の種類、金額の相場、そして渡し方を中心に解説いたします。
どのような品物が選ばれている?
現代の会葬返礼品として選ばれている品物は、ご参列いただいた方が「もらって嬉しい」「実用的」と感じられるものが中心となっています。具体的には、以下のような品物が人気を集めています。
- カタログギフト: 贈られた方が自分の好きなものを選べるため、大変喜ばれる定番の品物です。食品から日用品、体験ギフトまで幅広い選択肢があるため、年齢や好みを問わず贈ることができます。
- 食品: 保存がきき、日持ちするお菓子や、地域の名産品、こだわりの調味料などが選ばれています。ご家庭で気軽に楽しめるものが好まれる傾向にあります。
- 日用品: 上質なタオルや、実用的な石鹸、洗剤セットなども、日常的に使えるため人気があります。消耗品であることも、贈る側としては気遣いが感じられるポイントです。
これらの品物が選ばれる理由としては、ご参列いただいた方のライフスタイルに寄り添い、無駄なく活用していただけるものが重視されるようになったことが挙げられます。
金額の目安
会葬返礼品の金額の目安は、地域や葬儀の規模、ご遺族の意向によって異なりますが、一般的には1,000円程度が相場とされています。
特に、近年普及が進んでいる「即日返し」の場合、あらかじめ品物が決められていることが多いため、比較的均一な価格帯(3,000円〜4,000円程度)で用意されることが多いようです。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。ご遺族の経済状況や、故人との関係性などを考慮し、無理のない範囲で感謝の気持ちを伝えられる品物を選ぶことが大切です。
渡し方
会葬返礼品の渡し方には、いくつかの方法があり、それぞれに特徴があります。
- 通夜・告別式で渡す場合: 従来から行われている方法で、ご葬儀の受付や、読経終了後などに、ご遺族や葬儀スタッフがご参列者一人ひとりに手渡しします。
- 即日返し(当日返し): 近年最も一般的になっている方法です。通夜や告別式の当日に、ご参列いただいた方へあらかじめ用意した返礼品をお渡しします。香典の金額にかかわらず、全員に同じ品物を渡すのが一般的です。これにより、ご遺族は後日改めて香典返しを手配する手間を省くことができます。
- 後日郵送: 香典返しとして、ご葬儀後しばらくしてから品物を郵送する方法もあります。こちらは、香典をいただいた方への返礼として行われることが多く、会葬返礼品とは区別されます。
いずれの方法を選ぶにしても、感謝の気持ちを込めて、丁寧にお渡しすることが最も重要です。
会葬返礼品:清め塩の意味
葬儀に参列された方々へ感謝の気持ちを込めてお渡しする会葬返礼品ですが、その選び方には宗派による違いや、地域特有の風習が影響することがあります。
清め塩とは?
お清め塩とは、会葬者に渡される小さな塩のことです。お通夜や葬儀の後に、自宅へ入る前に身を清めるために使います。
古来、日本では死を穢れとみなし、塩で清める風習がありました。これは、葬儀で持ち帰った穢れを祓うためと考えられていました。お清め塩は神道の考え方に由来し、死を穢れとする神道では、その穢れを祓うために塩が用いられます。塩には古くから浄化や殺菌の力があるとされ、葬儀だけでなく災いの際にも用いられてきました。
会葬礼状の書き方
この度は、ご葬儀にご会葬いただき、誠にありがとうございました。ご参列いただいた皆様へ、心より感謝の意を伝えるための会葬礼状は、故人を偲ぶ大切な時間と共に、遺族の感謝の気持ちを伝える重要な役割を担います。ここでは、失礼なく、かつ心のこもった会葬礼状を作成するための基本的な構成、具体的な例文、そして作成時の注意点について詳しく解説いたします。故人への想いを胸に、感謝の言葉を丁寧に紡いでいきましょう。
基本的な構成
会葬礼状は、一般的に以下の要素で構成されます。これらの項目を自然な流れで配置することで、感謝の気持ちが伝わる礼状となります。
まず、冒頭には日付と、ご会葬いただいた方々への感謝の言葉を述べます。次に、故人の氏名とともに、永眠されたことへのご報告と、生前のご厚誼への感謝を伝えます。続いて、ご参列いただいたことへの重ねての御礼と、故人を偲ぶお気持ちへの感謝を記します。
結びには、ご遺族の近況や今後の抱負などを簡潔に添え、皆様のご健勝を祈る言葉で締めくくるのが一般的です。これらの要素を盛り込むことで、故人への敬意と参列者への感謝が伝わる、心のこもった会葬礼状を作成することができます。
例文
拝啓
〇月〇日、父 〇〇 儀 永眠いたしました ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます
早速ご参列いただき、ご丁重なるご香典・ご供花を賜り、 誠に有難く厚く御礼申し上げます
皆様にはご多忙中にもかかわらず ご会葬くださいましたことに、心より感謝申し上げます 故人もさぞかし喜んでおりますことと存じます
本来であれば、直接お伺いし、ご挨拶を申し上げるべきところ 略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
皆様の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇家 喪主 〇〇 〇〇
書く際の注意点
会葬礼状を作成する際には、いくつか注意しておきたい点があります。 まず、誤字脱字がないか、提出前に必ず複数回確認しましょう。些細なミスでも、相手に失礼な印象を与えてしまう可能性があります。
次に、忌み言葉の使用には十分注意が必要です。「重ね重ね」「くれぐれも」「追って」「再び」といった、不幸が繰り返されることを連想させる言葉や、「消える」「切れる」「終わる」といった、死を連想させる言葉は避けるべきです。
また、宗教や宗派によって、使用する言葉遣いや表現に違いがある場合があります。例えば、仏式では「冥福」、神式では「御霊前」、キリスト教式では「安らかな眠り」など、それぞれの教えに沿った表現を選ぶことが大切です。
最後に、例文を参考にしつつも、故人への想いやご遺族の気持ちを込めて、ご自身の言葉で感謝の気持ちを伝えることが何よりも重要です。心を込めて作成することで、参列者の方々への敬意と感謝がより一層伝わるでしょう。
香典返しのマナー
近親者の方が亡くなられた後、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える香典返しは、大切な儀礼の一つです。このセクションでは、香典返しの時期、金額の目安、品物選びのポイント、そして贈る際のマナーについて、失礼のない対応ができるよう、詳しく解説いたします。
香典返しの時期
香典返しを贈る時期は、一般的に四十九日(地域によっては三十五日や五十日)の法要を終えた後が目安とされています。これは、故人が無事に極楽浄土へ旅立つための期間と考えられているためです。ただし、地域や宗派によって異なる場合もありますので、迷われた際は菩提寺や近親者にご確認いただくと安心です。法要後、なるべく早めに準備を進めることで、感謝の気持ちを伝えることができます。
金額の目安
香典返しの金額の目安は、いただいた香典の半額(半返し)が一般的とされています。例えば、1万円の香典をいただいた場合は、5千円程度の品物をお返しするのが相場です。ただし、これはあくまで目安であり、地域性や故人との関係性、香典をいただいた方の状況なども考慮して調整することが大切です。高額な香典をいただいた場合や、連名でいただいた場合などは、無理のない範囲で感謝の気持ちが伝わる品物を選びましょう。
品物選びのポイント
香典返しの品物としては、「消えもの」と呼ばれる、後に残らないものが一般的です。食品(お菓子、海苔、お茶など)、洗剤、タオル、石鹸などがこれにあたります。これらは相手の好みに左右されにくく、気軽に受け取っていただけるため、多くの方に選ばれています。逆に、縁起が悪いとされる「忌み言葉」が含まれるものや、弔事の品としてふさわしくないものは避けましょう。近年では、カタログギフトも相手に好きなものを選んでいただけるため人気があります。
贈る際の注意点
香典返しを贈る際には、感謝の気持ちを伝える挨拶状を添えるのがマナーです。挨拶状には、お礼の言葉とともに、故人の名前や法要を終えた旨などを記載します。宗教や宗派によって、お返しの時期や品物、表書きなどが異なる場合があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。また、「重ね重ね」「度々」といった重ね言葉や、「、」「。」といった句読点は、不幸が重なることを連想させるため、挨拶状では使用を避けるのが一般的です。
即日返しについて
葬儀の形式が多様化し、簡略化が進む現代において、「即日返し」は注目を集める返礼品のマナーの一つです。これは、葬儀当日に参列者へ感謝の気持ちを込めて品物をお渡しする形式を指します。本稿では、この即日返しについて、そのメリットとデメリット、そして実施する上での注意点を詳しく解説し、皆様がご自身の状況に合わせて最適な選択ができるよう、分かりやすくご説明いたします。
即日返しのメリットとデメリット
即日返しを導入することには、いくつかの利点と考慮すべき点があります。まず、メリットとしては、参列者の方々がその場ですぐに感謝の品を受け取れるため、満足度が高まることが挙げられます。また、葬儀を執り行う側にとっても、後日改めて香典返しを手配する手間や、配送の手配、管理といった負担を軽減できるという大きな利点があります。 一方で、デメリットとして、参列者からいただいた香典の金額が、その場で判明しない場合があるという点が挙げられます。後日、高額な香典をいただいたことが分かった場合、当日の即日返しでは金額に見合わない品物になってしまう可能性も否定できません。このようなケースにどう対応するか、事前に検討しておくことが重要です。
注意点
即日返しを円滑に行い、後々のトラブルを防ぐためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。まず、品物の選び方ですが、参列者の皆様に喜んでいただけるような、日持ちがして、どなたにでも使いやすい品物を選ぶことが大切です。例えば、お菓子やタオル、日用品などが一般的です。 次に、金額設定も重要なポイントです。香典の金額とのバランスを考慮し、地域やご遺族の考え方に沿った適切な金額の品物を選ぶ必要があります。また、地域によっては即日返しが一般的でない場合や、特定の宗教・宗派において配慮が必要な場合もありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。ご不明な点があれば、葬儀社や地域の慣習に詳しい方に相談すると良いでしょう。
返礼品の選び方
故人を偲び、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える会葬返礼品や香典返し。どのような品物を選べば良いか、迷う方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、失礼なく、そして相手に喜んでいただける返礼品の選び方について、タブーとされる品物と人気のある品物を中心にご紹介します。
タブーとされる品物
香典返しや会葬返礼品を選ぶ際には、避けた方が良いとされる品物がいくつかあります。一般的に、「不祝儀(ぶしゅうぎ)」を連想させるものや、慶事(けいじ)に使われるものは、香典返しとしてはふさわしくありません。例えば、お酒は「故人の好きだったお酒を偲んで」といった特別な意図がない限り、避けるのが無難です。また、肉類や魚介類といった生鮮食品も、賞味期限や保存方法の点で相手に負担をかけてしまう可能性があるため、あまり推奨されません。さらに、派手な装飾が施されたものや、故人の趣味嗜好が強く反映された、受け取る人によっては好みが分かれるような品物も、相手への配慮を欠く可能性があるため注意が必要です。これらの品物は、受け取る方に気を使わせてしまったり、不快な思いをさせてしまったりする可能性があるため、慎重に検討しましょう。
人気のある品物
一方で、現代の会葬返礼品や香典返しでは、実用的で相手の好みに合わせやすい品物が人気を集めています。最も定番と言えるのは、やはりカタログギフトです。相手が自分の好きなものを選べるため、好みが分からない場合でも安心して贈ることができます。また、日用品としていくつあっても困らないタオル類も根強い人気があります。上質なタオルは、日常使いはもちろん、来客用としても喜ばれます。食品では、日持ちのするお菓子や、調味料、コーヒー・紅茶のセットなどが人気です。個包装になっているものなら、相手も自分のペースで楽しめます。洗剤や石鹸といった日用消耗品も、実用的で喜ばれる品物の一つです。これらは、いわゆる「消えもの」として、後に残らないため、相手に気を遣わせにくいというメリットもあります。これらの品物は、故人を偲ぶ気持ちを伝えつつ、相手に負担なく喜んでいただける、心遣いの表れとなるでしょう。
状況別の対応
いただいた香典やご会葬への感謝の気持ちを形にする会葬返礼品や香典返しは、故人との関係性やいただいたご厚志の金額など、状況に応じて適切な対応が求められます。ここでは、具体的なケースに沿って、どのように対応すれば良いのかを解説します。読者の皆様が、失礼なく、かつ感謝の気持ちをきちんと伝えられるような、最適な判断を下すための一助となれば幸いです。
香典の金額別
香典の金額は、会葬返礼品や香典返しの品物を選ぶ上で重要な基準となります。一般的に、会葬いただいた方には、当日お持ち帰りいただける「会葬返礼品」をお渡しします。これは、金額に関わらず、参列いただいたことへの感謝の印です。一方、「香典返し」は、いただいた香典の金額に応じて、後日品物をお返しするものです。 目安としては、いただいた香典の半額から1/3程度の品物をお返しするのが一般的とされています。例えば、3,000円の香典をいただいた場合は、1,000円から1,500円程度の品物、5,000円の場合は1,500円から2,500円程度の品物を選ぶと良いでしょう。ただし、これはあくまで目安であり、地域や習慣、故人との関係性によっても異なります。 また、高額な香典をいただいた場合でも、必ずしもその金額に見合った品物を返す必要はありません。大切なのは、感謝の気持ちを伝えることです。品物選びに迷った際は、カタログギフトなどを利用するのも一つの方法です。相手の好みに合わせて選んでもらえるため、喜ばれることが多いでしょう。
故人との関係性別
故人との関係性によって、会葬返礼品や香典返しの品物、そしてその渡し方にも配慮が必要です。 親族や親しい友人など、特に近しい関係の方からは、連名で高額な香典をいただくことも少なくありません。このような場合、会葬返礼品とは別に、改めて香典返しとして、いただいた金額に応じた品物をお返しするのが一般的です。品物の相場は、いただいた香典の半額から1/3程度が目安ですが、関係性の深さを考慮して、感謝の気持ちを込めて選ぶことが大切です。 一方、職場関係者や、あまり親しくなかった方々から香典をいただいた場合は、会葬返礼品のみで済ませることもあります。しかし、それでも一定以上の金額をいただいた場合は、個別に感謝の意を伝え、後日品物をお返しすることを検討しても良いでしょう。 渡し方についても、親族には直接手渡し、それ以外の方には郵送するなど、相手への配慮を忘れず、丁寧な対応を心がけましょう。品物には、感謝の気持ちを記した手紙を添えると、より一層気持ちが伝わります。
会葬返礼品に関するQ&A
葬儀に参列された方へ感謝の気持ちを伝える会葬返礼品や、香典をいただいた際のお返しである香典返しは、準備に迷うことも少なくありません。ここでは、多くの方が疑問に感じる点や、さらに深く知りたい情報をQ&A形式でまとめてご紹介します。この情報が、大切な故人を偲ぶお時間に集中するための一助となれば幸いです。
まとめ
本記事では、葬儀に際して準備が必要となる会葬返礼品、会葬礼状、そして香典返しについて、その基礎知識から近年の傾向、ふさわしいマナー、さらには選び方までを網羅的に解説いたしました。
この情報が、読者の皆様が葬儀の準備をよりスムーズに進め、参列された方々や故人の関係者に対して失礼のない、心遣いの行き届いた対応をとるための一助となれば幸いです。最終的な目標である「安心感の提供」を念頭に、この知識が皆様の不安を軽減し、大切な弔いの場を整える一助となることを願っております。
もしもの時の安心を、今、あなたに。
株式会社ライフサポートグループは、家族葬専門の「もみじ会館」をはじめ、「早良直葬センター」「大橋直葬センター」にて、低価格で良心的な葬儀サービスを提供しております。
突然のことで心が落ち着かない、そんな時でも安心して任せられる、きめ細やかなサポートをお約束いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 「費用を抑えて、心温まる葬儀をしたい」
- 「直葬や家族葬について詳しく知りたい」
- 「生前のうちに葬儀の準備をしておきたい」
ライフサポートグループにお任せください。
私たちは、お客様一人ひとりのご希望に寄り添い、納得のいく葬儀のお手伝いをいたします。生前契約サービスもご用意しており、お元気なうちから安心して葬儀の準備を進めることができます。
まずは、お気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、お客様のお悩みに丁寧にお答えいたします。
[家族葬もみじ会館] [092-477-0033] [福岡市南区高木1-16-27]
[大橋直葬センター] [もみじ会館内]
[早良直葬センター] [092-600-2632] [福岡市早良区飯倉3-1-26]
株式会社ライフサポートグループ [0120-78-1059]
【公式】福岡市の家族葬7万円|追加費用なし明朗会計|ライフサポート


 無料資料請求
無料資料請求











