トピックス
ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、
最新情報をお知らせしています。
2025年10月25日
【喪中】年末年始の挨拶、これで安心!マナーと文例、過ごし方の完全ガイド
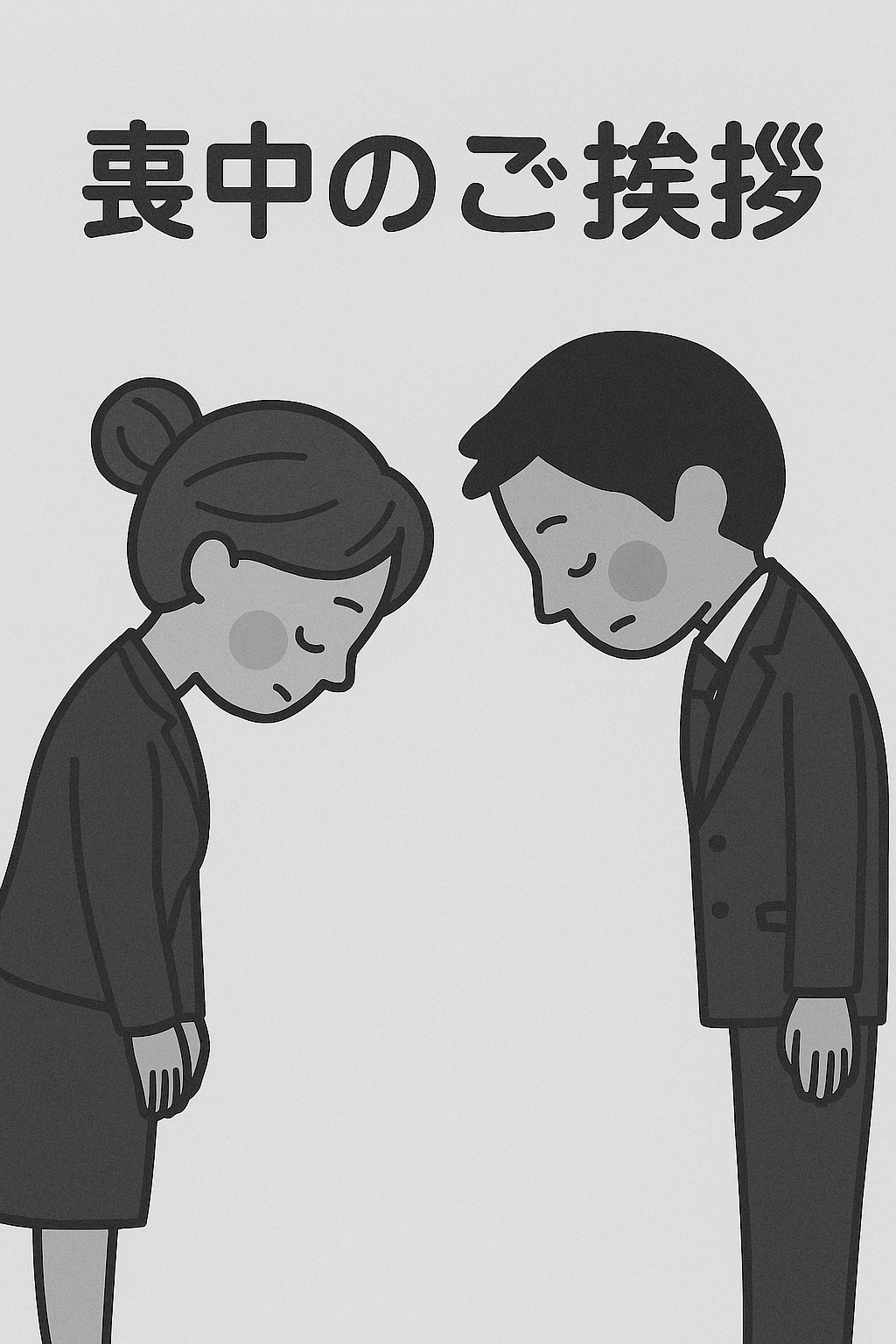
「喪中」という言葉が、あなたの大切な人を失った悲しみと、年末年始を迎えるにあたっての様々な不安を呼び起こすかもしれません。喪中の年末年始は、故人を偲び、静かに過ごす大切な時間です。この記事では、喪中の方が周囲に失礼なく、心穏やかに年末年始を過ごすためのマナーと過ごし方を、具体的な例文を交えながら分かりやすく解説します。年賀状、挨拶、親戚への連絡、お正月の過ごし方など、喪中に関する疑問を解消し、安心して新年を迎えられるよう、お手伝いします。
喪中とは?年末年始の挨拶を考える前に
近親者を亡くされた方が初めて迎える喪中の時期は、例年とは異なる心持ちで過ごす必要があります。特に、年末年始の挨拶や慣習について、どのように対応すれば失礼なく、故人を偲びながら穏やかな気持ちで過ごせるのか、多くの方が疑問に思われることでしょう。本セクションでは、喪中に関する基本的な知識と、年末年始の挨拶を控えるべき理由、そして具体的な伝え方について解説します。
喪中の期間
喪中とは、近親者が亡くなった際に、その死を悼み、身を慎む期間のことです。一般的に、仏教では故人の冥福を祈る四十九日(満中陰)までを忌中とし、その後、一周忌までを喪中とすることが多いですが、これはあくまで目安です。地域や家庭、故人との関係性によって、喪に服す期間は異なります。例えば、両親や配偶者を亡くした場合と、兄弟姉妹や祖父母などを亡くした場合では、期間の考え方が変わることもあります。現代では、一周忌までという期間にとらわれず、遺族の気持ちの整理がつくまで、あるいは社会的な慣習として、年末年始の挨拶を控える期間を指す場合も多くなっています。大切なのは、故人を偲ぶ気持ちを大切にし、無理のない範囲で過ごすことです。
喪中であることの伝え方
喪中であることを周囲に伝える方法はいくつかあります。最も一般的なのは「喪中はがき」を送る方法です。これは、年賀状をやり取りする予定だった方々へ、喪中であるため年賀のご挨拶を失礼する旨を伝えるための挨拶状です。例年11月下旬から12月初旬にかけて投函するのが一般的です。はがきには、亡くなった方の氏名、続柄、喪中であること、そして来年の年賀状を欠礼することなどを簡潔に記載します。
親しい友人や親戚など、より身近な方々へは、喪中はがきを送る前に、電話やメール、あるいは直接会った際に口頭で伝えることもあります。この場合、亡くなった事実と、喪中であるため年末年始の挨拶を控えたい旨を丁寧に伝えましょう。相手への配慮を示すことが大切です。どのような方法を選択するにしても、相手に不快感を与えず、かつ正確に情報を伝えることを心がけましょう。
年末年始の挨拶のマナー
近親者を亡くされた方が初めて迎える喪中の年末年始は、例年とは異なり、どのように過ごし、どのような挨拶をすれば良いか戸惑うことも少なくありません。故人を偲びつつ、周囲の方々への配慮も忘れずに、心穏やかに新年を迎えるためのマナーや注意点について、ここでは詳しく解説していきます。特に、年賀状のやり取りや、年末年始の挨拶における言葉遣い、親戚への連絡、お歳暮やお年玉といった具体的な対応について、失礼のない方法を確認していきましょう。
年賀状の対応
喪中の期間は、一般的に新年のお祝いの言葉を述べることを控えます。そのため、年賀状は送らないのが原則です。これは、故人への弔意を表し、遺族の悲しみに配慮するための慣習です。喪中期間は、一般的に故人が亡くなってから四十九日法要(満中陰)までとされることが多いですが、一周忌まで喪に服す場合もあります。年末に不幸があった場合、その年は喪中となり、翌年から通常の年賀状を出すことになります。ただし、地域や家庭によっては慣習が異なる場合もあるため、周りの方や親戚に確認することも大切です。
年賀状の書き方(喪中の場合)
喪中の期間に年賀状の代わりに送るのが「喪中欠礼状」です。これは、年賀状のやり取りを控える旨を、年賀状を出す予定だった方々へ事前に伝えるための挨拶状です。一般的には、11月下旬から12月初旬にかけて送付するのが良いとされています。 喪中欠礼状には、以下の要素を含めるのが一般的です。
- 時候の挨拶(「年の瀬も押し迫り」など、お祝いの言葉を避けたもの)
- 喪中である旨とその理由(「この度、〇〇(故人の続柄)である〇〇(故人の名前)が永眠いたしました」など、簡潔に)
- 喪中期間(「〇月〇日、〇歳で永眠いたしました」のように、故人の名前や日付、享年を記載するのが丁寧です)
- 来年の年賀状を欠礼させていただく旨(「つきましては、年末年始のご挨拶はご遠慮させていただきます」)
- 結びの言葉(「皆様にはご清祥のこととお慶び申し上げます」のような一般的な挨拶は避け、「皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます」といった、相手の健康を気遣う言葉を選びます)
- 日付、差出人の住所・氏名
年賀状が届いた場合の対応
喪中に年賀状を受け取った場合は、年賀状で返信することはできません。しかし、感謝の気持ちを伝えることは大切です。この場合、松の内(一般的には1月7日まで)を過ぎてから、「寒中見舞い」または「喪中見舞い」として返信するのが一般的です。 寒中見舞いは、寒さ厳しき折の挨拶として、喪中見舞いは、喪中であることを改めて伝え、故人を偲ぶ気持ちを表現するものです。 返信には、以下のような内容を含めると良いでしょう。
- 年賀状をいただいたことへの感謝の言葉
- 喪中であったため、年賀状での挨拶を欠礼したことへの断り
- 故人の冥福を祈る言葉や、遺族を気遣う言葉
- 相手の健康や多幸を祈る言葉
- 日付、差出人の住所・氏名
文例としては、「拝啓 寒さ厳しき折、皆様いかがお過ごしでしょうか。この度はご丁寧な年始のご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。さて、私儀、〇月〇日に〇〇(故人の続柄・名前)が永眠いたしましたため、年末年始のご挨拶を失礼させていただきました。〇〇(故人の名前)もさぞかし皆様の長寿を願っていたことと存じます。末筆ではございますが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 敬具」といった形になります。
挨拶の基本
近親者を亡くし、初めて喪中を迎える方が、年末年始の挨拶や過ごし方について、失礼なく、故人を偲びながら心穏やかに過ごすためのマナーや注意点、具体的な対応方法について解説します。特に、年賀状、挨拶の言葉遣い、親戚への連絡、お歳暮、お年玉、年末年始の過ごし方といった具体的な疑問を解消し、故人を偲びつつも、周囲との円滑なコミュニケーションを図るためのポイントを押さえます。
避けるべき言葉
喪中の期間に、お祝い事や不幸が重なることを連想させる言葉を使用することは避けるべきです。これは、故人への敬意を表し、遺族の悲しみに配慮するためです。具体的には、以下のような言葉が該当します。
- 慶事(けいじ)を連想させる言葉: 「めでたい」「祝う」「新年」「元旦」「初春」「福」「寿」「賀正」といった、お祝いや新しい始まりを意味する言葉は、喪中の期間にはふさわしくありません。
- 不幸が重なることを連想させる言葉: 「重ね重ね」「たびたび」「くれぐれも」「追って」など、不幸が続くことを連想させる表現は、遺族の心情に配慮し避けるべきです。
- その他: 弔問の際に用いられる「ご愁傷様です」といった言葉も、年明けの挨拶としては不適切です。
使える言葉と挨拶の例文
喪中でも使える、失礼なく、かつ故人を偲ぶ気持ちを伝えられる言葉や挨拶があります。年明けの挨拶は、お祝いの言葉を避け、故人を悼む気持ちを添えることが大切です。
- 年明けの挨拶: 「新年おめでとうございます」という直接的なお祝いの言葉の代わりに、「新年のお慶びを申し上げます」「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」といった表現を用いるのが一般的です。 また、「旧年中は大変お世話になりました」という感謝の言葉は、そのまま使用できます。
- 故人を偲ぶ言葉: 「この度はお悔やみ申し上げます」 「ご霊前にお供えいたします」 「〇〇様(故人)のご冥福を心よりお祈り申し上げます」
- 具体的な例文:
- 「新年のお慶びを申し上げます。旧年中は大変お世話になりました。〇〇様(故人)のご霊前にお供えいたします。」
- 「謹んで新年のご挨拶を申し上げます。この度はお悔やみ申し上げます。〇〇様(故人)のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」
状況別の挨拶例(親戚、会社、友人など)
挨拶は、相手との関係性や状況に応じて、適切な言葉遣いを選ぶことが重要です。ここでは、親戚、会社関係者、友人・知人といった、それぞれの関係性に応じた挨拶の例を、メールや口頭での伝え方を含めて紹介します。
- 親戚へ:
- 口頭での挨拶例: 「新年のお慶びを申し上げます。〇〇(故人)さんも、きっと安らかに過ごされていることでしょう。旧年中は大変お世話になりました。」
- メールでの挨拶例: 「拝啓 〇〇様。 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 この度はお悔やみ申し上げます。〇〇(故人)様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。 敬具」
- 会社の上司・同僚へ:
- 口頭での挨拶例: 「新年のお慶びを申し上げます。〇〇(故人)さんのご遺影に手を合わせ、静かに新年を迎えました。旧年中は大変お世話になりました。」
- メールでの挨拶例: 「〇〇部長 拝啓 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 旧年中は大変お世話になりました。 この度はお悔やみ申し上げます。〇〇(故人)様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 敬具」
- 友人・知人へ:
- 口頭での挨拶例: 「新年おめでとうございます。…(喪中である旨を伝え、本来ならお祝いの言葉だが、と前置きしつつ)…〇〇(故人)さんのことを偲びながら、静かに新年を迎えました。旧年中はお世話になりました。」
- メールでの挨拶例: 「〇〇様 新年のお慶びを申し上げます。 旧年中は大変お世話になりました。 この度はお悔やみ申し上げます。〇〇(故人)様のご冥福をお祈りいたします。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。」
親戚や知人への連絡方法
近親者を亡くされた直後は、多くの方が喪中という経験に慣れておらず、年末年始の挨拶や、親しい方々への連絡方法に悩まれることでしょう。故人を偲びつつ、失礼なく、そしてご自身が心穏やかに過ごすためには、適切な連絡方法を知ることが大切です。ここでは、親戚や知人へ喪中であることを伝える際の、タイミング、手段、そして具体的な伝え方について解説します。
連絡のタイミング
喪中であることを関係者に伝える一般的なタイミングは、年内に、できれば喪中はがきを出す時期(一般的に11月上旬から12月初旬)に合わせて行うのが望ましいとされています。これにより、相手はお正月の挨拶を控えることができます。しかし、急な訃報であった場合や、相手との関係性によっては、年明けに改めて伝えることもあります。例えば、ごく近しい親戚には、訃報があった際に直接伝えるのが最も丁寧ですが、年賀状をやり取りするような関係性であれば、喪中はがきで正式に伝えるのが一般的です。故人との関係が深い方や、お世話になった方には、早めに、そして丁寧に伝えることを心がけましょう。
連絡手段(手紙、メール、電話)
喪中であることを伝える手段は、相手との関係性や状況に応じて使い分けるのが一般的です。
- 喪中はがき(手紙):
- 適した相手: 年賀状のやり取りがある友人、知人、会社関係者、遠方の親戚など、比較的フォーマルな関係性の方。
- メリット: 正式な手段であり、丁寧な印象を与えます。相手がお正月の準備をする前に届くよう、時期を考慮して送ることができます。
- デメリット: 手配に時間がかかる場合があります。
- 電話:
- 適した相手: ごく近しい親戚、親しい友人、お世話になった方など、親密な関係性の方。
- メリット: 相手の状況を気遣いながら、直接声で伝えることができます。迅速に情報を伝えられます。
- デメリット: 相手が電話に出られる状況でない場合や、感情がこみ上げてしまう可能性もあります。
- メール・SNS:
- 適した相手: 若い世代の友人、SNSで繋がっている知人など、普段からメールやSNSでのやり取りが中心の方。
- メリット: 手軽に、かつ迅速に連絡できます。相手の都合の良い時間に確認してもらえます。
- デメリット: フォーマルな印象には欠けるため、相手や状況を選ぶ必要があります。目上の方や、改まった関係性の方には避けた方が無難です。
これらの手段を、相手への配慮を忘れずに選択することが大切です。
連絡の文例
喪中であることを伝える際には、故人への哀悼の意を示しつつ、簡潔に、そして相手への配慮を忘れずに伝えることが大切です。以下に、相手別の文例をいくつかご紹介します。
【親戚・親しい友人へ(電話や直接伝える場合)】 「この度、〇〇(故人の名前)が〇月〇日に永眠いたしました。生前は大変お世話になり、ありがとうございました。ただ今、喪中ですので、新年のご挨拶は失礼させていただきます。皆様もどうぞご自愛ください。」
【会社関係者・目上の方へ(喪中はがきの場合)】 (はがき表面) 〒XXX-XXXX (住所) (氏名)
(はがき裏面) 拝啓
〇〇の候、皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、この度〇月〇日に、父(または母、夫、妻など)〇〇儀、〇〇歳にて永眠いたしました。 ここに謹んでご通知申し上げますとともに、生前のご厚情に深く感謝申し上げます。 つきましては、年末年始のご挨拶を辞退させていただきます。 皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
本来であれば、皆様にお目にかかりご挨拶申し上げるべきところ、略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
〇〇年〇月〇日
(差出人名) 〒XXX-XXXX (住所) (氏名)
【友人・知人へ(メールの場合)】 件名:喪中につき年末年始のご挨拶を失礼させていただきます
〇〇様
いつもお世話になっております。△△(差出人の名前)です。
この度、祖母(または母、父など)〇〇が、〇月〇日に亡くなりました。 生前は大変お世話になり、心より感謝しております。
つきましては、年末年始のご挨拶は失礼させていただきます。 皆様におかれましても、どうぞご自愛ください。
〇〇(差出人の名前)
これらの文例はあくまで一例です。ご自身の言葉で、相手への敬意と感謝の気持ちを込めて伝えることが何よりも大切です。
喪中のお歳暮とお年玉
喪中とは、近親者が亡くなった際に、その死を悼み、冥福を祈る期間です。特に初めて喪中を経験される方は、年末年始の挨拶やお祝い事の習慣にどのように向き合えば良いか、戸惑うことも多いでしょう。お歳暮やお年玉といった、例年通りに行うことが一般的とされる慣習についても、喪中の期間にどのように対応するのが適切か、失礼なく、故人を偲びながら心穏やかに過ごすためのマナーや注意点について解説します。
お歳暮のマナー
喪中の期間にお歳暮を贈るべきか否かは、故人との関係性や喪中の深さ、そしてご自身の気持ちによって判断が分かれます。一般的には、故人が亡くなってから初めて迎える年末年始(新盆や法事の前など)は、お祝い事を避けるべき期間とされています。そのため、喪中にお歳暮を贈ることは控えるのが無難とされています。
しかし、相手との関係性を大切にしたい場合や、喪中期間が明けている、あるいは故人がご自身にとって直接的な近親者ではないといった理由で、お歳暮を贈りたいと考えることもあるでしょう。その場合は、時期を少しずらして、お歳暮の時期(12月初旬〜25日頃)を過ぎてから、あるいは松の内(1月7日頃まで)が明けた後などに贈るのが良いとされています。
また、品物を選ぶ際には、お祝い事を連想させる華やかなものや、食品の場合は日持ちのしない生鮮食品などは避けるのが賢明です。贈る際の表書きも重要で、「御歳暮」ではなく、「御霊前」「御供」「お世話になりました」といった、弔意を示す言葉を選ぶか、あるいは無地のしで贈るのが一般的です。相手に喪中であることを伝えたい場合は、品物に添える挨拶状でその旨を伝えることもできます。
お年玉のマナー
お年玉は、子供たちの健やかな成長を願うお正月の楽しみの一つですが、喪中の期間に渡すかどうかは、お歳暮と同様に慎重な判断が求められます。一般的には、故人が亡くなってから間もない時期や、喪中の期間が続いている場合は、お年玉を渡すことは控えるのが望ましいとされています。これは、お年玉がお祝いの性質を持つため、喪中の雰囲気にそぐわないと考えられるからです。
しかし、子供が小さく、お年玉を楽しみにしている場合や、喪中の期間が既に明けている、あるいは故人がご自身にとって直接的な近親者ではないといった状況であれば、渡すことを検討しても良いでしょう。その場合でも、金額は一般的な相場よりも控えめにすることが推奨されます。また、お札を入れるポチ袋も、派手なキャラクターものや、お祝いの柄が入ったものは避け、無地や落ち着いた色合いのシンプルなものを選ぶのが良いでしょう。
表書きについては、「お年玉」と書くのが一般的ですが、喪中の期間であることを考慮し、子供の名前だけを書く、あるいは「お年玉」と書いた上に小さく「おめでとう」などを添えるといった配慮も考えられます。ただし、地域や家庭の習慣によっても異なるため、ご家族や親戚と相談して決めるのが最も安心です。
お歳暮・お年玉のマナー比較
| 項目 | 喪中の場合 | 一般的な場合 |
|---|---|---|
| お歳暮 | 贈らないのが一般的です。贈る場合は、時期をずらすか、表書きを「御霊前」「御供」などにし、お祝い事を連想させる品物は避ける配慮が必要です。 | 12月1日から25日頃までに、日頃の感謝を込めて贈ります。 |
| お年玉 | 贈らないのが一般的です。贈る場合は、金額を控えめにしたり、品物にするなどの配慮が求められます。ポチ袋はシンプルなものを選びます。 | 子供の健やかな成長を願って、お正月に贈ります。 |
年末年始の過ごし方の注意点
近親者を亡くし、初めて喪中を迎える方にとって、年末年始の挨拶や過ごし方は特別な配慮が必要です。故人を偲びながらも、社会的な慣習の中で失礼なく、心穏やかに過ごすためのマナーや注意点、具体的な対応方法について解説します。
外出時の注意点
喪中の期間、特に初めて迎える年末年始では、初詣や初日の出鑑賞、旅行といった外出を控えるべきか悩む方が多いでしょう。一般的に、これらの行事は新年を祝うためのものであり、喪中の期間にはふさわしくないとされる場合が多いです。初詣や初日の出鑑賞は、華やかな雰囲気を伴うため、避けるのが無難です。どうしても近隣の神社仏閣に参拝する必要がある場合は、静かに手を合わせる程度に留め、おみくじを引いたりお守りを購入したりする行為は控えます。旅行に関しても、リゾートや観光地への長旅は、故人を偲ぶ時期としては不向きです。やむを得ず外出する際は、派手な服装を避け、落ち着いた色合いの服装を選び、常に故人を偲ぶ心を忘れないように心がけましょう。
正月行事について
年末年始には、門松や鏡餅といった正月飾りを飾ったり、おせち料理を食べたり、親戚が集まる機会があったりと、様々な行事があります。喪中の期間にこれらの行事をどう扱うかは、故人への敬意と、周囲への配慮が求められます。一般的に、門松や鏡餅などの正月飾りは、新年を祝う象徴であるため、喪中の家庭では飾りません。おせち料理についても、華やかな祝い膳は控えるのが基本ですが、家族だけで静かにいただく場合や、故人が生前好んだ料理を供養の意味でいただくことは、許容されることもあります。親戚の集まりに参加する際は、お祝いムードに乗りすぎず、故人の思い出を語り合うなど、落ち着いた時間を過ごすことが大切です。
食事について
喪中の年末年始における食事は、日常の食事よりも少し丁寧にする必要はありますが、お祝い膳のような華やかなものは避けるべきです。故人を偲ぶ時期ですから、派手な食材や調理法を用いた料理ではなく、質素で滋味深い食事を心がけると良いでしょう。もし、親戚や知人からお祝いの料理をいただく機会があった場合は、感謝の気持ちを伝えつつ、少量いただくか、丁重にお断りするのがマナーです。また、故人が生前好きだった料理を準備し、静かに供養するというのも、故人を偲ぶ良い方法と言えるでしょう。大切なのは、食事を通して故人を思い、穏やかな時間を過ごすことです。
喪中を心穏やかに過ごすために
初めて喪中を経験される方は、年末年始の挨拶や日々の過ごし方について、どのように対応すれば失礼なく、故人を偲びながら心穏やかに過ごせるか、多くの疑問や不安を抱えることでしょう。このセクションでは、喪中の期間を大切に過ごすための心構えと具体的な方法について解説します。
故人を偲ぶ時間
故人を失った悲しみと向き合い、穏やかな気持ちで日々を過ごすためには、意識的に故人を偲ぶ時間を持つことが大切です。これは、故人との思い出を振り返り、感謝の気持ちを再確認する貴重な機会となります。具体的には、故人の遺影や写真を見返しながら、楽しかった日々を思い出したり、故人が好きだった場所を静かに訪ねたりすることが挙げられます。また、故人の遺品を整理したり、手紙を読み返したりすることも、故人の存在を身近に感じ、心の整理をつける助けとなるでしょう。無理に感情を抑え込まず、ご自身のペースで故人との絆を確かめる時間を持つことが、前を向くための第一歩となります。
周囲の理解を得る
喪中であることを周囲に理解してもらうことは、誤解を防ぎ、心穏やかに過ごすために重要です。特に、年賀状のやり取りや年末年始の集まりなど、例年とは異なる対応が必要になる場合があります。親しい友人や職場の上司・同僚などには、喪中であることを簡潔に伝え、年末年始の挨拶を控える旨を伝えるのが一般的です。伝え方としては、直接話す、電話、またはメールなどが考えられます。無理に詳細を説明する必要はありませんが、失礼な印象を与えないよう、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また、精神的に辛い時には、信頼できる家族や友人にサポートをお願いすることも大切です。一人で抱え込まず、周囲の理解と協力を得ながら、この時期を乗り越えていきましょう。
専門家への相談
喪失感や悲しみ、不安が強く、日常生活に支障が出ていると感じる場合は、一人で抱え込まずに専門家のサポートを求めることを検討してください。悲嘆(グリーフ)の専門家であるカウンセラーや心理士は、あなたの感情に寄り添い、心のケアをサポートしてくれます。また、葬儀や法事に関する相談はもちろん、仏事や法要、喪中の過ごし方全般について、経験に基づいたアドバイスを得たい場合は、葬儀社や菩提寺の僧侶に相談するのも良いでしょう。自治体によっては、心の健康相談窓口を設けている場合もあります。専門家の力を借りることは、決して恥ずかしいことではなく、ご自身の心を大切にするための賢明な選択です。
まとめ
近親者を亡くされた喪中の年末年始は、例年とは異なる特別な期間となります。初めて喪中を経験される方は、どのように過ごし、どのように振る舞えば失礼にあたらないか、不安を感じることでしょう。この期間は、故人を偲び、心静かに過ごすことを大切にしながらも、社会的な慣習や親族との関わりも考慮する必要があります。年賀状の送付を控える、新年の挨拶を簡潔にする、お歳暮やお年玉といった慣習への配慮など、基本的なマナーを理解し、周囲への配慮を忘れずに過ごすことが、故人への供養にもつながります。このまとめでは、喪中の年末年始を心穏やかに、かつ失礼なく過ごすための要点を改めて確認します。
喪中はがき印刷 2025年(令和7年)|郵便局のプリントサービス
もう郵便局では「喪中はがき」が買えない?2025年の最新事情と正しい出し方(マミ) – エキスパート – Yahoo!ニュース


 無料資料請求
無料資料請求











