トピックス
ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、
最新情報をお知らせしています。
2025年10月19日
葬儀の食事完全ガイド:通夜ぶるまい、お斎、精進落とし…マナーと料理のすべて
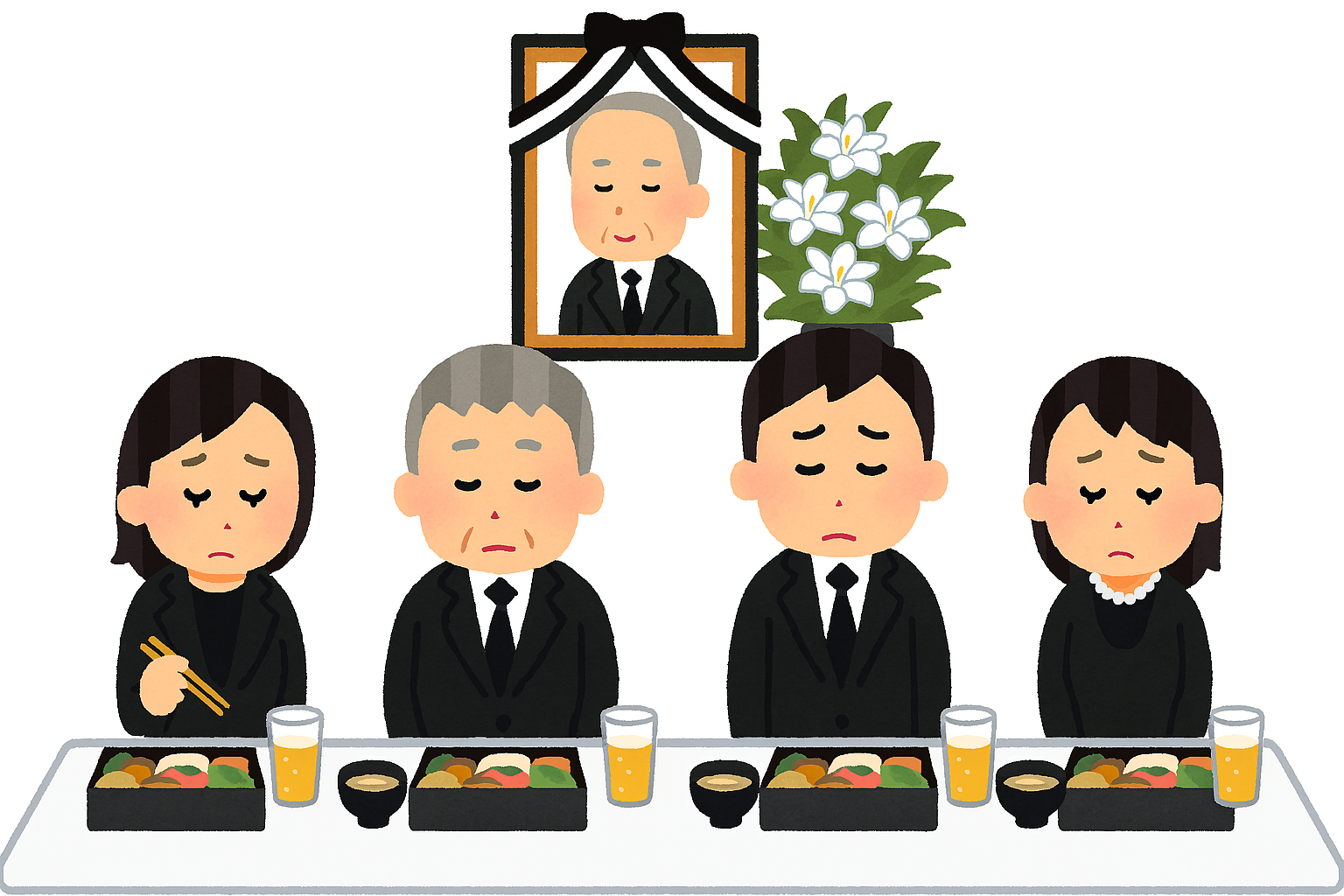
「葬儀に参列することになったけど、食事ってどんなものを用意すればいいの?」 故人との最後の時間を過ごす葬儀。大切な方との別れを悲しみ、様々な準備に追われる中で、食事に関する疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、葬儀の食事である通夜ぶるまい、お斎、精進落とし、御料具膳について、その違いやマナー、具体的な料理の例、費用の目安まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、葬儀の食事に関する不安を解消し、故人との大切な時間を心穏やかに過ごすことができるでしょう。
葬儀の食事の種類と目的
葬儀の際にご提供される食事には、故人を偲び、参列者をもてなすための様々な種類があります。通夜ぶるまい、お斎(おとき)、精進落とし、御料具膳といった食事は、それぞれ提供されるタイミングや目的が異なります。これらの食事の違いを理解することで、葬儀の儀式や風習への理解を深めることができます。本セクションでは、それぞれの食事の定義、目的、そしてどのような場面で提供されるのかを詳しく解説します。
通夜ぶるまいとは
通夜ぶるまいは、通夜の儀式が終わった後に、参列してくださった方々への感謝の意を込めて提供される食事です。故人の霊を慰めるとともに、参列者同士が故人を偲びながら語り合う場としての役割も担います。一般的には、寿司、煮物、和え物、茶碗蒸し、吸い物などが用意され、参列者は立食形式または着席形式で、無理のない範囲で飲食します。通夜ぶるまいは、故人の冥福を祈る一連の儀式の一部として、参列者への配慮を示す大切な習慣です。
お斎とは
お斎(おとき)は、火葬後や初七日法要、四十九日法要などの法要後、僧侶や親族、故人と縁の深かった方々を招いて行われる食事のことです。故人を供養し、集まった人々が労をねぎらい、故人の思い出を語り合う目的があります。地域や宗派によって、提供されるタイミングや形式は異なりますが、一般的には法要が終わった後に、参列者へ感謝の意を込めて振る舞われます。精進料理が基本とされることが多いですが、最近では形式にとらわれず、通常の食事に近いものを提供する場合もあります。
精進落としとは
精進落としは、四十九日法要など、忌明けの法要を済ませた後に行われる食事会です。これまでの間、故人のために肉や魚などの生臭いものを断つ「精進料理」で過ごしてきた期間が終わり、通常の食事に戻ることを意味します。そのため、精進落としは、忌明けを迎え、区切りをつけるための慶事としての意味合いも持ちます。参列者には、故人を偲びつつも、新たな生活への一歩を踏み出す区切りとして、食事とともに感謝の気持ちが伝えられます。
御料具膳とは
御料具膳(ごりょうぐぜん)は、精進料理とは異なり、故人を供養するための特別な膳として提供される食事の一種です。かつては僧侶など、特別な方々に対して、より丁寧なもてなしとして提供されることが多かったとされます。その内容は、精進料理の形式にとらわれず、魚や肉を含む場合もあり、見た目も豪華で、故人への敬意を表す意味合いが込められています。現代では、地域や風習によってその提供の有無や内容は異なりますが、故人を偲び、感謝の気持ちを表すための食事として理解されています。
葬儀の食事で提供される料理
葬儀では、故人を偲び、参列者をもてなすために様々な食事が出されます。通夜ぶるまい、お斎、精進落とし、御料具膳といった、それぞれの食事の場面で提供される代表的な料理の例を具体的にご紹介します。これらの料理は、故人を供養する意味合いだけでなく、参列者同士の語らいの場を和やかにする役割も担っています。
通夜ぶるまいの料理例
通夜ぶるまいでは、参列者への感謝の気持ちを表し、故人を偲びながら食事を共にするのが一般的です。ここでは、通夜ぶるまいでよく提供される代表的な料理の例をいくつかご紹介します。
- 寿司: 握り寿司や巻き寿司は、手軽につまめる人気のメニューです。
- オードブル: チーズ、ハム、カナッペなど、洋風の軽食も用意されることがあります。
- 和え物: 季節の野菜を使った和え物は、箸休めにぴったりです。
- 煮物: 故人の好きだったものや、温かい煮物は心を落ち着かせます。
- 茶碗蒸し: 滑らかな舌触りの茶碗蒸しは、幅広い年齢層に喜ばれます。
お斎の料理例
お斎(おとき)は、火葬後や初七日法要の後などに、僧侶や親族、世話になった人々に食事を振る舞う儀式です。地域や宗派によって内容は異なりますが、精進料理が中心となることが多いです。
- 精進料理: 豆腐、野菜、きのこ、海藻などを使った、肉や魚を使わない料理が基本です。
- 炊き合わせ: 季節の野菜を上品なだしで炊き合わせたものです。
- 和え物・酢の物: 彩りも良く、さっぱりとした味わいです。
- ご飯・汁物: 炊き込みご飯や白米、お吸い物などが添えられます。
- 地域によっては: 精進料理ではなく、通常の会席料理が提供される場合もあります。
精進落としの料理例
精進落としは、法要がすべて終わり、故人の霊が迷わず成仏することを願うとともに、遺族が忌明けを迎えたことを親族や親しい人々に報告し、労をねぎらうための食事です。忌明けを祝う意味合いも含まれるため、これまでの精進料理とは異なり、華やかな料理が並ぶこともあります。
- 刺身: 新鮮な魚介類を使った刺身は、お祝いの席にふさわしい一品です。
- 煮物: 鯛や海老など、縁起の良い食材を使った煮物もよく見られます。
- 揚げ物: 天ぷらや唐揚げなど、食欲をそそる揚げ物も人気です。
- ちらし寿司・手巻き寿司: 華やかな見た目のちらし寿司や、皆で楽しめる手巻き寿司も用意されます。
- 汁物: 蛤のお吸い物など、お祝いの席にふさわしい汁物が添えられます。
御料具膳の内容
御料具膳(ごりょうぐぜん)は、主に皇族や一部の旧華族などが用いた、格式高い儀式で提供される特別な膳です。一般の葬儀で提供されることは稀ですが、その内容は非常に豪華で、伝統的な日本料理の粋を集めたものとなります。
- 主食: 炊き込みご飯や赤飯など、特別な日のためのご飯が用意されます。
- 焼き物: 鯛や伊勢海老など、縁起の良い魚介類が丸ごと一匹、またはその一部が焼かれます。
- 煮物: 季節の高級食材を使った、繊細な味わいの煮物が出されます。
- 刺身: 新鮮で上質な刺身は、御料具膳の定番です。
- 吸い物: 丁寧にとられた出汁を使った、上品な吸い物が提供されます。
- その他: 季節の野菜を使った和え物、果物、菓子などが彩り豊かに盛り付けられます。https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/osonae-oryouguzen?srsltid=AfmBOop76W3L5cVibz3IOZsQuTyD9A1XYwaukLYIgw4SmpCnX6L7VlTH
葬儀の食事の準備とマナー
葬儀の際、参列者をもてなす食事は、故人を偲び、遺族を労う大切な機会です。しかし、その準備や振る舞いには、地域や宗派、慣習によって様々な配慮が求められます。ここでは、葬儀の食事における準備方法、守るべきマナー、費用の目安、そして地域による違いについて詳しく解説します。これらの知識を持つことで、より心を込めたお見送りができるでしょう。
食事の準備方法(手配、持ち込み)
葬儀の食事は、一般的に葬儀社が提供するサービスを利用するか、仕出し弁当などを手配することが多いです。葬儀社に依頼する場合、通夜ぶるまいやお斎(おとき)といった、会食の場に合わせた料理や飲み物の準備を一任できます。祭壇の横などに設けられる会食スペースでの提供や、ご自宅での食事会に対応してくれる場合もあります。
一方、ご遺族が個人的に用意した飲食物を持ち込む(持ち込み)については、葬儀場や斎場の規定によります。持ち込みが可能な場合でも、匂いの強いものや、量が多いものは他の参列者への配慮が必要です。準備を進める際は、まず葬儀社に相談し、持ち込みの可否や、どのような手配が可能かを確認することが最も確実な方法です。会食の規模や予算に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
食事のマナー(席次、挨拶、配慮すべきこと)
葬儀での食事は、故人を偲ぶ場であり、参列者同士が故人の思い出を語り合う貴重な時間です。そのため、いくつかのマナーを守ることが大切です。
- 席次(せきじ)
- 一般的に、上座にはご遺族や親族、故人と特に親しかった方などが座ります。空いている席があれば、周囲に確認してから着席しましょう。
- 席が決まっている場合は、指示に従います。
- 挨拶
- 料理が運ばれてきた際や、食事を始める前には、喪主や遺族に対して「お疲れ様です」「頂戴いたします」などの一言を添えると丁寧です。
- 他の参列者と話す際は、故人の思い出話を中心に、穏やかなトーンで話しましょう。
- 配慮すべきこと
- 料理は取りすぎず、食べきれる分だけを取ります。残さず食べるのが基本ですが、どうしても食べきれない場合は、無理に食べる必要はありません。
- 大声で話したり、騒いだりすることは避け、静かに食事を楽しみます。
- アレルギーや苦手な食材がある場合は、無理せず、周囲に配慮して食べます。可能であれば、事前に遺族や葬儀社に伝えておくと安心です。
- 通夜ぶるまいは、故人の生前の功績を偲び、弔問客をもてなすためのものです。お斎は、火葬後や初七日法要後に行われる会食で、故人を偲びながら食事をします。
- 食事中は、携帯電話の電源を切るかマナーモードにし、通話は控えましょう。
費用相場(目安、内訳)
葬儀の食事にかかる費用は、地域、葬儀の規模、料理の内容によって大きく異なります。一般的に、一人あたりの目安として、数千円から1万円程度が相場とされています。以下に、一般的な費用目安を示しますが、あくまで参考としてください。
| 食事の種類 | 一人あたりの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 通夜ぶるまいの軽食 | 2,000円~3,000円 | おにぎり、サンドイッチ、茶碗蒸し、吸い物など |
| 弁当・仕出し | 3,000円~5,000円 | 複数のおかずが入った幕の内弁当、ちらし寿司など |
| 会席料理 | 5,000円~10,000円 | 刺身、焼き物、煮物、揚げ物、ご飯、汁物、デザートなど、コース仕立て |
| 飲み物 | 1,000円~2,000円 | ビール、日本酒、ソフトドリンクなど(飲み放題の場合も含む) |
費用の内訳としては、料理自体の材料費や調理費、配膳スタッフの人件費、会場費(食事スペース利用料)などが含まれます。葬儀社によっては、これらの項目を細かく提示してくれる場合もありますので、見積もりを取る際に確認すると良いでしょう。
地域による違い
葬儀の食事は、その土地の風習や郷土料理が色濃く反映されることがあります。地域によって「通夜ぶるまい」や「お斎」の習慣が異なり、提供される料理やマナーにも違いが見られます。
例えば、北日本では魚介類を使った料理が豊富であったり、西日本では精進料理に地域独特の工夫が凝らされていたりします。また、一部の地域では、故人の好物だったものを供えたり、特定の縁起の良いとされる料理を避けるといった風習がある場合もあります。
地域差を理解することは、その土地の文化や人々の思いに触れることにも繋がります。もし、遠方の地域で葬儀に参列する機会がある場合は、事前にその地域の風習について調べておくと、よりスムーズに、そして敬意をもって参列することができるでしょう。不明な点があれば、地元の葬儀社や、その地域の慣習に詳しい方に尋ねるのが一番です。
精進揚げのレシピ
この記事では、家庭で簡単に作れる「精進揚げ」のレシピをご紹介します。読者の「自分で作れる料理のレシピを知りたい」というニーズに応えるため、材料、作り方、美味しく仕上げるポイントを、写真や動画を参考に解説します。
材料
精進揚げを作るために必要な材料は以下の通りです。
- 季節の野菜(かぼちゃ、ナス、ピーマン、さつまいもなど):適量
- 豆腐や厚揚げ(水切りしたもの):適量
- 小麦粉:100g
- 冷水:150ml(衣の固さを見ながら調整)
- 塩:少々
- こしょう:少々
- 揚げ油:適量
作り方
精進揚げの調理手順を、ステップごとに分かりやすく解説します。動画での詳しい解説もご用意していますので、ぜひ参考にしてください。
- 下準備: 季節の野菜や豆腐を食べやすい大きさに切ります。野菜は火の通りにくいものから順に切ると均一に仕上がります。
- 衣を作る: ボウルに小麦粉、塩、こしょうを入れ、冷水を加えてさっくりと混ぜ合わせます。混ぜすぎるとグルテンが出てしまうので注意しましょう。衣は少しだまが残る程度が目安です。
- 具材に衣をつける: 切った野菜や豆腐に、手順2で作った衣をしっかりと絡めます。
- 揚げる: 揚げ油を170℃に熱し、衣をつけた具材を静かに投入します。一度にたくさん入れすぎると油の温度が下がるので、数回に分けて揚げましょう。
- 仕上げ: 具材がきつね色になり、衣がカリッとしたら、油から取り出し、しっかりと油を切ります。
ポイント
美味しく作るためのコツや、注意点などを解説します。完成イメージは、参考画像をご覧ください。
- 衣のサクサク感: 衣を作る際は、冷水を使うことと、混ぜすぎないことがサクサクとした食感の秘訣です。
- 油の温度管理: 揚げ油の温度は170℃を保つようにします。温度が低すぎると油っぽくなり、高すぎると焦げ付きやすくなります。温度計があると便利です。
- 具材の火の通り: 野菜の種類によって火の通り方が異なります。かぼちゃやかぶのような火の通りにくいものは、揚げる前に軽く電子レンジで加熱しておくと均一に火が通ります。
- 油を切る: 揚げ終わった後は、網などに乗せてしっかりと油を切ることで、べたつきを防ぎ、より美味しくいただけます。https://domani.shogakukan.co.jp/866816
葬儀の食事に関するQ&A
葬儀での食事は、故人を偲び、参列者同士が語り合う大切な時間です。しかし、そのマナーや費用、内容について疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。ここでは、よくある質問にお答えし、読者の皆様の不安を解消します。
葬儀での食事マナーについて
Q. 葬儀での食事中に、特に気を付けるべきマナーはありますか? A. 葬儀での食事は、故人を偲ぶ場であることを忘れず、落ち着いた態度で臨むことが大切です。基本的には、静かに食事をいただき、大声での会話は控えましょう。料理が出されたら、残さずいただくのが礼儀とされています。お酒を飲む場合も、節度を守りましょう。また、食事の場所によっては、私語厳禁の場合もありますので、周りの状況を見て判断してください。
葬儀の食事の費用相場
Q. 葬儀の食事にかかる費用は、だいたいどのくらいが相場ですか? A. 葬儀の食事にかかる費用は、地域や葬儀の規模、料理の内容によって大きく異なりますが、一般的には一人あたり3,000円~7,000円程度が相場とされています。会席料理や仕出し弁当など、選択肢によっても費用は変動します。事前に葬儀社や料理業者に相談し、予算に合ったプランを検討することをおすすめします。
葬儀で提供される食事の種類
Q. 葬儀では、どのような種類の食事が提供されることが多いですか? A. 伝統的には「精進料理」が提供されることが一般的でしたが、近年では形式にとらわれず、会席料理や仕出し弁当など、故人の遺志や参列者の状況に合わせて多様化しています。温かい料理やお寿司、麺類などが用意されることもあります。アレルギーや宗教上の理由で食べられないものがある場合は、事前に葬儀社に伝えておくと配慮してもらえることがあります。
食事に関するアレルギーや制限への対応
Q. 参列者にアレルギーを持つ方や、食事制限のある方がいる場合、どうすれば良いですか? A. 事前に参列者の人数や、アレルギー、宗教上の理由、健康状態による食事制限の有無などを把握し、葬儀社や料理業者に伝えておくことが重要です。可能な範囲で、個別の対応(アレルギー対応食、ベジタリアン対応食など)を依頼することができます。事前に確認・相談しておくことで、安心して食事を楽しんでいただけるよう配慮しましょう。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
お見積もり・資料請求 | 【公式】福岡市の家族葬7万円|追加費用なし明朗会計|ライフサポート


 無料資料請求
無料資料請求











