トピックス
ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、
最新情報をお知らせしています。
2025年10月18日
葬儀で後悔しない!知っておくべきNGワードと、心に響くお悔やみの言葉
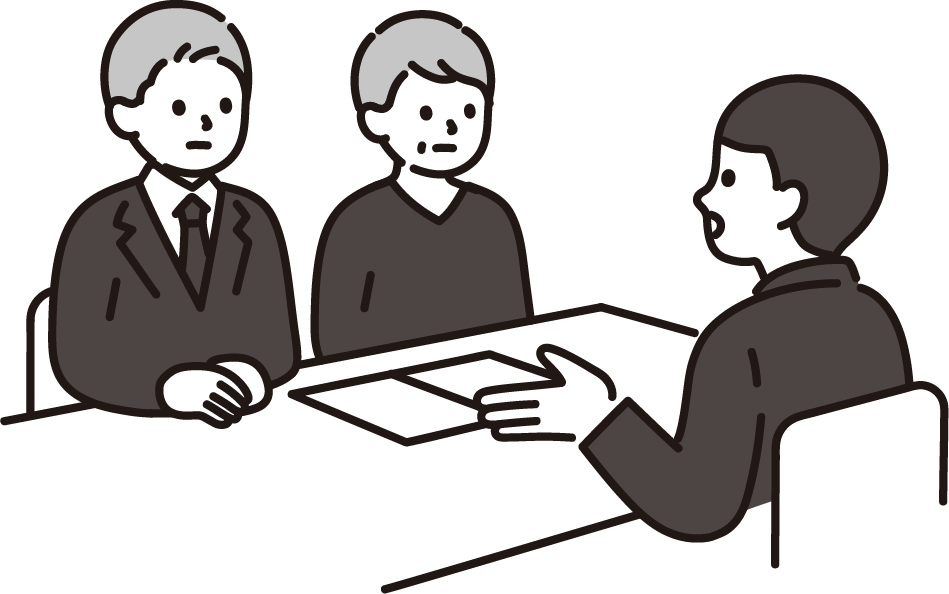
大切な人の葬儀に参列することになったけれど、「何か失礼なことを言ってしまったらどうしよう…」と不安に感じていませんか?
故人の冥福を祈り、遺族の方々の心を少しでも癒したい。誰もがそう願うからこそ、葬儀での言葉選びは非常に重要です。この記事では、葬儀で「言ってはいけないNGワード」を具体的に解説し、状況別の適切な言葉遣い、心に響くお悔やみの言葉を紹介します。この記事を読めば、葬儀に自信を持って参列し、故人を偲ぶ心と、遺族への心遣いを両立できるでしょう。
葬儀で絶対に避けるべき「NGワード」とは?
読者は葬儀で失礼な言葉を使わないか不安を感じており、具体的にどのような言葉がNGなのかを知りたいと考えています。ここでは、直接的な死の表現、不幸が重なることを連想させる言葉、宗教・宗派によって不適切な言葉など、避けるべきNGワードを具体例とともに解説します。読者の不安を解消し、適切な言葉遣いを身につけるための基礎となります。
直接的な死を連想させる言葉
葬儀の場では、直接的に「死ぬ」「生きる」といった言葉を使うことは避けるのが一般的です。これらの言葉は、遺族の悲しみを直接的に刺激したり、死を連想させたりするため、不謹慎だと受け取られる可能性があります。代わりに、「亡くなる」「逝去される」「永眠される」といった、より丁寧で婉曲的な表現を用いることが推奨されます。また、故人の冥福を祈る際にも、「成仏する」といった言葉は仏教以外の宗教では適切でない場合があるため、相手の信仰に配慮することが大切です。
不幸を重ねることを連想させる言葉
「重ね重ね」「たびたび」「くれぐれも」といった、同じような言葉を繰り返す「重ね言葉」は、不幸が重なることを連想させるため、葬儀の場では忌み言葉として使用を避けるべきです。お悔やみの言葉を伝える際には、これらの言葉を使わずに、遺族の悲しみに寄り添う丁寧な言葉を選ぶことが大切です。例えば、「この度は心よりお悔やみ申し上げます」といったシンプルな表現が適切です。
宗教・宗派によっては不適切な言葉
お悔やみの言葉として一般的に使われる「ご冥福をお祈りします」という言葉も、仏教の教えでは死後、すぐに冥福が得られるとは限らないという考え方があるため、浄土真宗など一部の宗派では使わないのがマナーとされています。この場合、「お悔やみ申し上げます」「ご愁傷様です」といった、より一般的な表現を用いるのが無難です。宗教や宗派によって、死生観や死後の世界に関する考え方が異なるため、相手の信仰に配慮した言葉遣いが求められます。例えば、浄土真宗では「往生される」という表現が使われることもあります。
NGワードを使ってしまった場合の対処法
万が一、不適切な言葉遣いをしてしまった場合、慌てずに落ち着いて対処することが重要です。ここでは、事態を悪化させず、読者の不安を軽減するための具体的なアクションと、誠意ある対応のポイントを解説します。
素直な謝罪と誠意ある態度
まず、間違いを犯したことを素直に認め、関係者に対して誠意をもって謝罪することが最も重要です。言い訳をしたり、責任を回避しようとしたりする態度は、事態をさらに悪化させる可能性があります。迅速かつ率直な謝罪は、信頼回復への第一歩となります。
具体的なアクション
謝罪と同時に、再発防止策を明確に伝えることも大切です。どのような点に注意し、今後どのように改善していくのかを示すことで、読者はあなたの真摯な姿勢を理解し、信頼を取り戻すきっかけになります。
誠意ある対応を心がけることで、失われた信頼を回復し、より健全なコミュニケーションを築くことができます。
状況別!正しい言葉遣いとマナー
葬儀参列の機会が増え、マナーに自信がない読者に対し、具体的な場面での適切な言葉遣いと、言葉以外の基本的なマナーを解説します。弔問、焼香、通夜・告別式での挨拶といった具体的なシーン別に、失礼なく、かつ遺族に寄り添うための対応方法を提供し、読者の不安を解消します。
弔問時の言葉
葬儀前や後などに遺族宅へ弔問する際の、適切な挨拶や声かけの例を解説します。遺族は深い悲しみの中にいるため、配慮ある言葉を選びましょう。訪問する際は、事前に連絡を入れるのがマナーです。
「この度は心よりお悔やみ申し上げます。」
「〇〇様のご霊前にお悔やみ申し上げます。」
「ご愁傷様です。どうぞお力落としください。」
(※弔問の際は、故人の名前を呼びすぎないように注意しましょう。)
焼香時の言葉
焼香を行う際に、どのような言葉を添えるべきか、あるいは不要なのかを解説します。一般的に、焼香の際には特別な言葉は必要ありません。静かに手を合わせるだけで十分です。もし言葉を添えたい場合は、ごく短く、遺族に配慮した言葉を選びましょう。
「お悔やみ申し上げます。」
「ご冥福をお祈りいたします。」
(※宗派によっては「ご冥福をお祈りいたします」が適切でない場合もありますので、不安な場合は何も言わないのが無難です。)
通夜・告別式での挨拶
通夜や告別式で遺族に会った際の、簡潔で丁寧な挨拶の仕方を解説します。遺族は悲しみや疲労の中にいるため、長話は避け、相手の心情を慮った短い言葉を選びましょう。受付を済ませた後、祭壇に向かう前や、式が始まる前に声をかけるのが一般的です。
「この度はご愁傷様です。」
「心よりお悔やみ申し上げます。」
「ご無理なさらないでください。」
(※「重ね重ね」「たびたび」などの重ね言葉は、不幸が重なることを連想させるため避けます。)
言葉以外の基本的なマナー
服装、香典の渡し方、会場での振る舞いなど、言葉遣い以外の葬儀における基本的なマナーを解説します。
- 服装:
- 男性:黒の無地のスーツに白シャツ、黒無地のネクタイを着用します。靴下や靴も黒で統一します。
- 女性:黒の無地のワンピース、アンサンブル、スーツなどを着用します。肌の露出は控えめにし、黒のストッキングを着用します。アクセサリーは結婚指輪以外は外すのが一般的です。
- 香典の渡し方:
- 香典は不祝儀袋に入れ、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。
- 受付では、袱紗から不祝儀袋を取り出し、相手から表書きが見えるようにして「御霊前(または御香典)です」と一言添えて渡します。
- 会場での振る舞い:
- 携帯電話はマナーモードにするか、事前に電源を切っておきましょう。
- 会場内での私語は慎み、静かに過ごします。
- 焼香の順番が来たら、係員の指示に従い、祭壇に進んで行います。
- 遺族に声をかける際は、相手の負担にならないよう、短く簡潔に済ませましょう。
葬儀マナーチェックリスト
遺族の心に寄り添う、お悔やみの言葉
遺族の悲しみに寄り添い、心を癒すような言葉は、かけがえのない支えとなります。定型的なお悔やみの言葉だけでなく、故人の功績を称えたり、遺族への深い気遣いを示したりする、よりパーソナルで温かい言葉の選び方を知ることは、参列者にとって重要な役割です。ここでは、読者が自信を持って遺族に寄り添えるよう、具体的な表現例を豊富に紹介します。
パーソナルなお悔やみの言葉のポイント
お悔やみの言葉は、故人との関係性や、遺族との関係性を踏まえて、心を込めて伝えることが大切です。故人の良い思い出や、その方が地域や仕事で果たした功績に触れることで、故人を偲ぶことができます。また、遺族の心労を気遣い、「何かできることがあればいつでも言ってください」といった具体的なサポートの申し出も、温かい気持ちを伝える助けとなります。
心に響いた言葉:体験談
先日、長年お世話になった恩師のお葬式に参列した際、一人の卒業生が「先生からいただいた〇〇という言葉が、今の私を支えています」と、具体的なエピソードを交えながら感謝の言葉を述べていました。その言葉は、恩師が生前、多くの人に影響を与え、温かい教えを広めていたことを物語っており、遺族の方々も静かに頷きながら、その言葉に耳を傾けていました。単なる形式的な挨拶ではなく、故人への敬意と感謝がこもった言葉は、参列者全員の心に深く響きました。
専門家からのアドバイス
葬儀アドバイザーの佐藤さんは、「お悔やみの言葉に『正解』はありません。大切なのは、表面的な言葉ではなく、故人や遺族への真摯な気持ちを伝えることです。故人の名前を呼び、具体的な思い出に触れることで、よりパーソナルなメッセージになります。また、遺族が感情的になっている場合や、多くの人に囲まれている場合は、簡潔に、そして相手のペースに合わせて言葉を選ぶ配慮も必要です」と語ります。僧侶の方々も、遺族の心情に寄り添い、故人を悼む気持ちを丁寧に伝えることを推奨しています。
具体的なお悔やみの言葉例
以下に、故人を偲び、遺族を気遣うための具体的な表現例をいくつか示します。これらの例文を参考に、ご自身の言葉でアレンジしてみてください。
故人を偲んで:
「〇〇様のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。」
「〇〇様とは、△△の件で大変お世話になりました。その節はありがとうございました。」
「〇〇様の明るいお人柄が偲ばれ、残念でなりません。」
遺族を気遣って:
「ご遺族の皆様におかれましては、さぞご心痛のこととお察しいたします。」
「どうぞご無理なさらないでください。何か私にできることがございましたら、いつでもお声がけください。」
「今はただ、心安らかにお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。」
まとめ
この記事では、葬儀で避けるべきNGワード、代わりに使える丁寧な表現、状況に応じたマナー、そして遺族に寄り添う言葉遣いについて解説しました。これらの知識を身につけることで、読者は自信を持って葬儀に参列し、故人を適切に弔い、遺族への深い配慮を示すことができるでしょう。この記事の目的は、読者が心からの哀悼の意を表し、大切な方を見送る一助となることです。
喪主挨拶の禁句一覧、タブーになるNGワード一気に確認できます [喪主ログ]
今すぐ、無料相談のお申し込みはこちらをクリック!
LINE相談お問い合わせ | 福岡市内で葬儀・家族葬をするなら ライフサポート
株式会社ライフサポート:直営式場はこちら


 無料資料請求
無料資料請求











